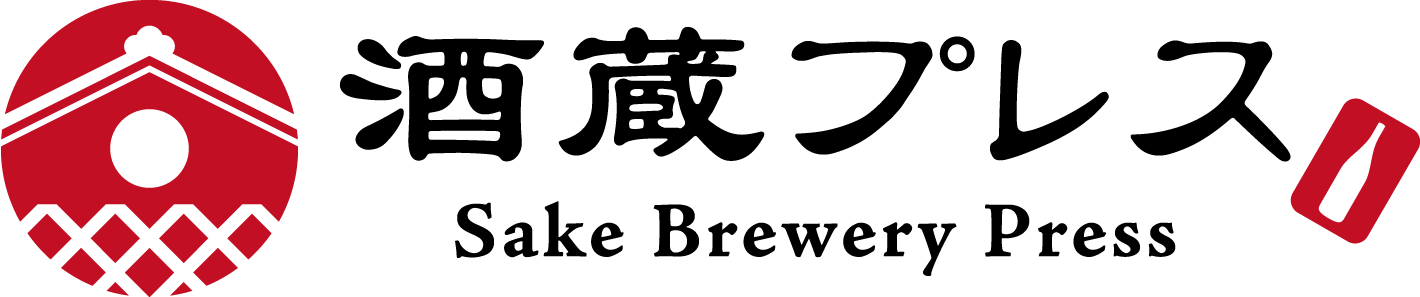料理研究家・辰巳芳子さん、95歳。
今も包丁を手に取りつつ、食といのちのかかわりに思索を廻らす日々。
そんな辰巳さんの「酒の肴づくりは、文化を生きる人間の、もっとも洗煉された表現行為なのではないか」という気づきから始まった随筆集が岩波書店から発売されました。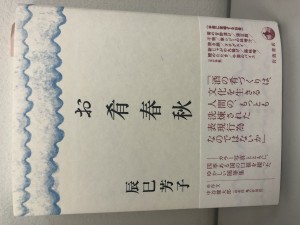
「食はいのちを養うものであれ」
本作の中で辰巳さんは、
身を労(ねぎら)い、精神の昂(たか)ぶりを宥(なだ)める食べ物としては特におつゆ、スープをお勧めしてきましたが、魂を癒(い)やすものとしてのお酒、お肴を欠かすことは、はやり難しいように思われます。
思えば酒の肴づくりは、文化を生きる人間のもっとも洗練された表現行為といえるかもしれません。
と綴っています。
料理研究家として95年の人生を歩んだ辰巳さんにとって、酒の肴はどこか「人間」らしさが現れる面白いものだそうです。
そんな魂を癒やすものとしてのお酒・お肴とはいかなるものでしょうか。
Ⅰ 読む肴 篇
四月 筍三昧
五月 花と風の月
六月 雨を聴く日々
七月 夏を迎え撃つ
八月 八月十五日のトマトジュース
九月 目にはさやかに見えねども
十月 菊の盃
十一月 風仕事
十二月 歳暮の滋味
一月 いやしけ吉事
二月 寒の美味
三月 春をいただく
Ⅱ 作る肴 篇
最初の一と品
いつもの肴
干 物
揚げ物
ちょっと一膳
おつゆ
漬 物
辰巳さんは本書の中で、かつてイタリアで料理を学んだ際の生ハムとの出会い、その後の日本での生ハムづくりの研究について触れています。生ハムは「頭脳と人の手、時間が生み出す究極の熟れ味(こなれあじ)」だといいます。赤ワインに合うのはもちろんのこと、生ハムが肴、ことにお燗を付けた日本酒と良く合うと気づいた時のことを丁寧な言葉で綴っています。
お気に入りの器に肴を少しのせて、お酒と共に仲間との会話を楽しむことは何物にも代えがたいこと。
95歳の料理研究家の知恵と言葉は奥深い。ぜひお手に取ってみてはいかがでしょうか。
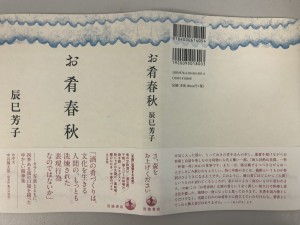
■本の詳しい紹介
https://www.iwanami.co.jp/book/b505579.html
■辰巳芳子(たつみ よしこ)
https://www.tatsumiyoshiko.com/
1924年、東京生まれ。料理研究家、随筆家。料理研究家であった母・辰巳浜子から家庭料理を、宮内庁大膳寮で修行した加藤正之からフランス料理を学ぶ。
NPO 法人「大豆100粒運動を支える会」会長、「確かな味を造る会」最高顧問。ドキュメンタリー映画「天のしずく 辰巳芳子“いのちのスープ”」(2012年、監督・河邑厚徳)のほか、『あなたのために』『仕込みもの』(ともに文化出版局)など、著書多数。