【キラリと光る、地域で愛される酒蔵の銘酒】全国にある様々な酒蔵の歴史と文化、オススメの商品や地域の観光をご紹介!
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と日本酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画がスタートしました!
日本には約1,400の酒蔵があり、地域の蔵人たちは日々情熱を注いで酒造りをしています。
そんな47都道府県の酒蔵のストーリーや銘酒、地域の観光をご紹介します。
こちらのページでは日々更新される連載ページを一覧とマップでご紹介します。日本酒選びや地元の酒蔵を知りたいときなどにお役立てください。
もしかしたら、旅行のときに役立つ情報があるかもしれません。
北海道
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第231回目の当記事では、北海道旭川市(あさひかわし)の男山(おとこやま)を特集します。 自然の贈り物、北海道の誇り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1887年に北海道で創業。もっと良い酒を造りたいとの想いで1968年、「木綿屋」本家の山本家より『男山』を正統継承しました。以来、北海道の自然の恵みを生かした酒造りで、名酒の味を現代に受け継いでいます。 1977年、日本酒では世界初となるモンドセレクション ...
「ここにしかないモノ」を造り続ける旭川の老舗酒蔵【国士無双】髙砂酒造‐北海道
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第137回目の当記事では、北海道旭川市(あさひかわし)の髙砂酒造(たかさごしゅぞう)を特集します。 「北海の灘」で北海道の米を使用した酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1899年に創業した旭川の地酒蔵。厳寒の地、北海道旭川市には酒造りに於いて有用な気候風土が整っており、古くより「北海の灘」と呼ばれるほど、多くの酒蔵が酒造りを行っていました。 沈降と堆積作用によって貯えられた良質豊富な地下水は、季節 ...
青森県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第221回目の当記事では、青森県三戸郡(さんのへぐん)の八戸酒類(はちのへしゅるい)を特集します。 新旧の伝統、「如空」の酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 昭和19年に戦時企業統制令により、近隣の蔵定5社が集まり共同設立で八戸酒類株式会社を立ち上げました。その後八戸酒類株式会社五戸工場と改め、新銘柄「如空」を以前と変わらず同じ蔵で仕込み、酒造りに励んでおります。 「ピュアで端麗」「ふくよかな旨味」 ...
青森県産酒造好適米豊盃米で醸す唯一無二の蔵【豊盃】三浦酒造‐青森県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第204回目の当記事では、青森県弘前市(ひろさきし)の三浦酒造(みうらしゅぞう)を特集します。 四季が織り成す、城下町弘前の酒蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業は昭和5年で城下町弘前では一番のベンチャー企業です。 春は弘前城の桜祭り、夏は弘前ねぷた祭り、秋は弘前城菊と紅葉祭り、冬は弘前城雪燈籠祭りと四季がきっちり別れておりそれぞれにお祭りが有ります。 冬は寒くお酒の仕込みに適し、夏は盆地なので熱く ...
「時代の枠に捉われない、青森県の原材料を使った様々なお酒を造る蔵」【陸奥八仙】八戸酒造‐青森県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第159回目の当記事では、青森県八戸市の陸奥八仙(むつはっせん)を特集します。 伝統と革新が紡ぐ、美味と安心の酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 当蔵は、元文年間、初代駒井庄三郎が青雲の志で近江の国を出、陸奥の地にて酒造りの道に入りました。安永4年(1775)から酒造業を開始以来、蔵元代々酒を造り続けてきました。 現在、8代目庄三郎は青森県の地酒として県産の米と酵母にこだわり、仕込み水は八戸・蟹沢地 ...
地元の水と米、地元出身の杜氏で造る本物の地酒【鳩正宗、八甲田おろし】鳩正宗株式会社-青森県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第39回目の当記事では、青森県十和田市 (あおもりけんとわだし)の鳩正宗(はとまさむね)を特集します。 青森県十和田市唯一の蔵元 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1899年(明治32年)稲本商店醸造部として創業し、青森県十和田市唯一の蔵元として地域に親しまれてきました。 厳しい気候風土で主に馬の放牧地帯としてしか使えず、人が住むには適していませんでしたが、掘削された人工河川「稲生川(いなおいがわ)」がで ...
新しい挑戦をしながら酒質を向上させていく酒造り【津軽じょんから、華一風】株式会社カネタ玉田酒造店-青森県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第35回目の当記事では、青森県弘前市(あおもりけんひろさきし)のカネタ玉田酒造店(かねたたまだしゅぞうてん)を特集します。 飲酒習慣者が多く青森県民は大のお酒好き ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 年間300石製造。弘前の城下町にある創業1685年(貞享2年)津軽4代藩主信政公より、玉田善兵衛に資金を出し酒屋を営ませたのが始まりであります。 「カネ玉」の屋号で長年親しまれた後、分家が大正期に興した「カネタ ...
地域に根ざした多彩な酒造り【駒泉、七力、作田、雪中八甲田】株式会社盛田庄兵衛-青森県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第21回目の当記事では、青森県上北郡(あおもりけんかみきたぐん)の盛田庄兵衛(もりたしょうべえ)を特集します。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 近江高島から北廻船でのみちのく青森七戸へ渡世。安永6年(1777年)創業となります。代々盛田庄兵衛を襲名して参りました。(現社長11代目は初代平治兵衛を襲名) 七戸地方は、平安の和歌に読まれた尾駮の駒、宇治川の戦いでの武将の乗馬、近代はダービー馬の産地として知ら ...
岩手県
世の人々が嬉しくなる一番の酒造りを目指して【世嬉の一】世嬉の一酒造-岩手県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第193回目の当記事では、岩手県一関市(いちのせきし)の世嬉の一酒造(せきのいちしゅぞう)を特集します。 歴史を守り、未来を創る酒蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 大正7年に創業した酒蔵です。祖父の代で倒産の危機にありましたが、三代目が蔵を改築して博物館・直売所・郷土料理レストラン・クラフトビール工場をつくり生きながらえました。(酒蔵は共同醸造にしていました。)今年40年ぶりに酒蔵復活を挑戦しています ...
「 日本三代杜氏の一つ「南部杜氏」が世界遺産・平泉の地で造る酒 」【関山】両磐酒造‐岩手県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第173回目の当記事では、岩手県西磐井郡(にしいわいぐん)の両磐酒造(りょうばんしゅぞう)を特集します。 平泉の魂を宿す、奥深き味わいの酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1944年、一関管内酒造業者が企業合同で発足。西磐井・東磐井の両方の磐の字をとり社名を両磐酒造株式会社としました。 両磐酒造を代表する「清酒 関山」の名は世界遺産の地、平泉に所縁があります。 およそ900年前の十二世紀、藤原初代秀衡公 ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第130回目の当記事では、岩手県二戸市(にのへし)の南部美人(なんぶびじん)を特集します。 山々に囲まれた風光明媚な蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 蔵がある岩手県二戸市は、周囲が山々に囲まれた風光明媚な場所に位置しています。豊臣の天下統一にいたる、最後の戦場にもなった九戸城跡、二戸一の山、折爪岳(オリツメダケ)には夏ヒメボタルが煌びやかに舞い、そこから流れ出した伏流水は様々な恩恵を受け、春は山の幸、 ...
宮城県
「 昼夜を問わない24時間体制の酒造り、伝統の技と手づくりにこだわる酒蔵」【 一ノ蔵 】 一ノ蔵 ‐宮城県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第153回目の当記事では、宮城県大崎市の一ノ蔵(いちのくら)を特集します。 世界農業遺産に認定された自然と調和する蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 昭和47年、宮城県内の歴史ある酒造家四社の若手経営者が“良酒づくり日本一”の蔵を志そうと合同し、『一ノ蔵』が誕生しました。 2017年に世界農業遺産に認定された大崎耕土の東、大崎市松山に蔵を構えております。森林丘陵と田園風景を持つこの町は、古くから農業と醸 ...
地元の魚を美味しくする酒【於茂多加男山、四季の松島、阿部勘】阿部勘酒造-宮城県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第116回目の当記事では、宮城県塩竈市(みやぎけんしおがまし)の阿部勘酒造(あべかんしゅぞう)株式会社を特集します。 寿司屋の数が日本一ともいわれる魚の町に創業した酒造所 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1716年(享保元年)に仙台藩の命により奥州一ノ宮塩竈神社の御神酒御用酒屋として創業いたしました。蔵のある宮城県塩竈市は古くから海運業、漁業が栄え人口当たりの寿司屋の数が日本一ともいわれる魚の町です。 ...
創業101年の地域に根付く酒造りと新たな挑戦【澤乃泉】石越醸造-宮城県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第112回目の当記事では、宮城県登米市(みやぎけんとめし)の石越醸造(いしこしじょうぞう)株式会社を特集します。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 弊社は大正9年に地元有志4人で米を持ち寄って酒造りを開始しました。戦時中も企業整備を免れ、現在まで社業を続けられております。 登米市は古くは伊達藩北の穀倉地帯として栄え、今ではひとめぼれやつや姫などの稲作、また仙台牛の産地としても有名で農業産出額は東北地方第2 ...
伝統と先進が融合する酒造り【雪の松島、大和蔵】大和蔵酒造-宮城県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第94回目の当記事では、宮城県黒川郡(みやぎけんくろかわぐん)の大和蔵酒造(たいわぐらしゅぞう)株式会社を特集します。 平成8年創業の新しい酒蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 弊社、大和蔵酒造株式会社は平成8年創業の新しい酒蔵です。 宮城県黒川郡大和町(たいわちょう)に蔵を構え、町名から名前を取り、大和蔵(たいわぐら)と命名されました。歴史は浅いですが、徐々に力をつけ国内外の数々の鑑評会で好成績を収め ...
秋田県
雪深い名水百選の地、秋田・湯沢で酒造り一筋に400年 【福小町】木村酒造‐秋田県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第271回目の当記事では、秋田県湯沢市(ゆざわし)の木村酒造(きむらしゅぞう)を特集します。 豊臣家重臣から400年続く伝統 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 元和元年(1615)年、豊臣家の重臣木村重成の一族が大阪夏の陣を機に秋田湯沢に居を移して造り酒屋を創業。 以来400余年、酒造り一筋の歩みを続けています。 江戸時代には当主が銘醸地伊丹に赴き酒造技術を学んだ後、現地より杜氏を招いたほか、山形県の大山 ...
呑み手も、造り手も、みんな愉しく【まんさくの花】日の丸醸造‐秋田県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第230回目の当記事では、秋田県横手市(よこてし)の日の丸醸造(ひのまるじょうぞう)を特集します。 登録有形文化財蔵、唯一無二の「まんさくの花」 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 元禄2年(1689年)創業。蔵名の「日の丸」は秋田藩主佐竹公の紋所が”五本骨の扇に日の丸”だったことに由来し、明治40年に商標登録済みの唯一無二の酒銘である。 現在の代表銘柄「まんさくの花」は、昭和56年に同名の朝の連続テレビ小 ...
目指すのは“地元でできる最高の酒”【鳥海山】天寿酒造‐秋田県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第226回目の当記事では、秋田県由利本荘市(ゆりほんじょうし)の天寿酒造(てんじゅしゅぞう)を特集します。 百歳の幸福、長寿の願い:奥深い味わい ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 天寿酒造は文政13年(1830年)初代大井永吉が麗峰鳥海山の麓、由利本荘市矢島町に創業し190余年の歴史がある蔵です。当主は代々永吉を名乗り、現在は七代目が継いでおります。 主銘柄「天寿」は百歳までも幸せに生きる事の意味であり、 ...
「 若い社員の力が結集した温故知新の酒造り 」【秋田晴】秋田酒造株式会社‐秋田県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第147回目の当記事では、秋田県秋田市の秋田晴 (あきたばれ)を特集します。 新屋の湧水から生まれた、伝統ある秋田地酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 秋田市新屋はかつて秋田地酒発祥の地として知られており、酒の産地として名を馳せていました。新屋は湧水の町として知られています。海岸沿いの砂丘地にあり、現在も町のいたるところに豊富な湧水や井戸が点在しています。 また、雄物川の河口付近に位置した、船着場であっ ...
地の「米」「水」「人」。秋田県五城目町で醸す酒造り【一白水成】福禄寿酒造-秋田県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第75回目の当記事では、秋田県南秋田郡 (あきたけんみなみあきたぐん)の福禄寿酒造(ふくろくじゅしゅぞう)株式会社を特集します。 今年2021年は創業333年の節目の年 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 当社・福禄寿酒造がある秋田県五城目町(ごじょうめまち)は、なまはげで有名な男鹿半島(おがはんとう)、昔は日本で2番目に広い湖であった八郎潟(はちろうがた)の東に位置した町です。 町のシンボルである森山(標 ...
秋田の自然と伝統の製法を最大に活かした酒造り【北秋田】北鹿-秋田県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第61回目の当記事では、秋田県大館市(あきたけんおおだてし)の株式会社北鹿(ほくしか)を特集します。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 昭和19年に、政府の企業整備により北秋田郡と鹿角郡(かづのぐん)の21業者8工場が合同し業を起こし、その両郡の頭文字を合わせ「北鹿(ほくしか)」と命名されています。 秋田県北部に広がる穀倉地帯の中心大館市に位置します。北西部には世界遺産の白神山地が古くから変わらぬ姿を残し ...
山形県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第198回目の当記事では、山形県米沢市(よねざわし)の小嶋総本店(こじまそうほんてん)を特集します。 全量純米の誇り、米沢の日の出の味わい ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 安土桃山時代(慶長2年・西暦1597年)に創業した、日本に現存する中で13番目に古い酒蔵で、江戸時代から上杉家御用酒屋を承わり、現蔵元である小嶋健市郎は24代目となります。酒名である「東光」は、米沢城から見た日の出の方角に酒蔵が位置す ...
創業江戸享保年間 山寺山形紅花文化テロワール醸造の老舗酒蔵【霞城寿】寿虎屋酒造‐山形県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第194回目の当記事では、山形県山形市の寿虎屋酒造(ことぶきとらや)を特集します。 ジブリ映画の舞台、心温まる300年の歴史 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 江戸享保年間1715年から創業、東北唯一の譜代大名城である山形城の御用酒屋として門前東旧三の丸内に位置する七日町で酒造り一筋300有余年の老舗酒蔵。(安土桃山時代頃から酒蔵は存在していた様だが、明治44年5月8日山形歴史史上に残る市北の大火に巻き込 ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第157回目の当記事では、山形県寒河江市の銀嶺月山(ぎんれいがっさん)を特集します。 地元農家との絆、豊かな大自然の中で育まれる蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 蔵の歴史は古く、元禄年間(1700年)「豊龍蔵」が酒造りを始めました。昭和47年さらなる品質向上を目指し、現在の地に月山酒造を創業しました。 山形県のほぼ中央出羽三山の主峰月山の麓に酒蔵があります。日本で一、二の広大な広大なブナの原生林を背景 ...
「 創業130周年「吟醸酒」のパイオニア酒蔵」【出羽桜】出羽桜酒造‐山形県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第155回目の当記事では、山形県天童市の出羽桜(でわざくら)を特集します。 品質と情熱、吟醸酒の魅力を広める ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 出羽桜酒造は明治25年(1892年)に初代仲野清次郎が分家し、酒蔵として創業致しました。それ以来、地元に根ざした品質第一の酒造りに徹し、1980年には、蔵の看板酒である「桜花吟醸酒」を発売致しました。 当時「吟醸酒」という言葉は一般的に知る人が少なく、鑑評会用にの ...
クラシックな素材から、過去に生きない酒を造る、創業300年の酒蔵が挑むニュークラシックな日本酒造り【吾有事】奥羽自慢株式会社‐山形県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第138回目の当記事では、山形県鶴岡市(つるおかし)の奥羽自慢(おううじまん)を特集します。 若き醸造責任者が打ち出す新ブランド『吾有事』 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1724年(享保9年)から続く、老舗酒蔵が直面した経営難。庄内の酒文化を守るべく隣町の楯の川酒造が蔵を引き継ぎました。 2017年に弱冠26歳にて現役員「阿部龍弥」が醸造責任者に就任、新ブランド「吾有事」を立ち上げました。「吾有事」は ...
「温故知新」と「不易流行」の伝統酒蔵【出羽ノ雪、和田来、庄内美人】渡會本店-山形県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第133回目の当記事では、山形県鶴岡市(つるおかし)の渡會本店(わたらいほんてん)を特集します。 山形県内の銘醸地である伝統な酒蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 当社は元和年間(1615年~1624年)創業、現当主(渡會俊仁)で十八代目となる山形県内でも伝統のある酒蔵です。蔵の立地する鶴岡市大山地区は古くから酒造りの町として知られた銘醸地で、最盛期には40軒以上の酒蔵が軒を連ねていました。 また江戸時 ...
地元農家とタッグを組み、米作りからの酒造りに邁進する創業300余年の老舗酒蔵【米鶴】米鶴酒造-山形県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第128回目の当記事では、山形県東置賜郡(ひがしおきたまぐん)の米鶴酒造(よねつる)を特集します。 オリジナル酒米「亀粋」を開発した蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1700年頃創業、米沢上杉藩御用酒屋の歴史を持つ山形県高畠町の日本酒醸造元です。全国酒類調味食品品評会で1968年に山形県内初のダイヤモンド賞受賞をはじめ、180を超える受賞歴で長年にわたり品質の高さを評価いただいております。 緑豊か、水 ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第125回目の当記事では、山形県東根市(ひがしねし)の六歌仙(ろっかせん)を特集します。 多彩なラインナップを取り揃え、時代に合った技術革新の蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 六歌仙は、さくらんぼの生産量日本一で有名な山形県東根市の酒蔵です。 奥羽山脈を背景に、肥沃な土地と豊かな湧き水に恵まれた環境で、山形県産米にこだわった酒を醸しています。 地域の酒蔵5蔵が合わさり、新しい酒造会社「六歌仙」が立ち上 ...
人と人、人と酒との調和が奏でる 「愛」 を心に【大山】加藤嘉八郎酒造株式会社-山形県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第42回目の当記事では、山形県鶴岡市(やまがたけんつるおかし)の加藤嘉八郎酒造(かとうかはちろうしゅぞう)を特集します。 江戸時代、 四十数軒の酒蔵が軒を連ねる東北随一の銘醸地 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 「豊かな米」、「清らかな水」、「厳しい冬の寒さ」と、酒造りに必要なものが全て揃った山形県庄内地方の大山の地で明治五年に創業しました。 江戸時代、庄内藩(しょうないはん)の中でも大山町は幕府直轄の天 ...
一口飲めば微笑みが浮かぶ様な自由な酒を醸す酒造り【九郎左衛門、雅山流、泉氷鑑、羽陽富久鶴】有限会社新藤酒造店-山形県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第33回目の当記事では、山形県米沢市(やまがたけんよねざわし)の新藤酒造店(しんどうしゅぞうてん)を特集します。 当代で10代目現在も全国有数の水の豊かな稲作地帯であり、付近には前田慶次に由来する清水も残っています。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 米沢市の東部の古くは伊達政宗が納めた天領だった場所に位置しています。庄屋を生業として傍らで酒造りをしてきたが、明治維新後に5代目が本業を酒造業としました。当 ...
福島県
小さい蔵ですが、福島県で、一番古い蔵【会州一】会州一酒造‐福島県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第279回目の当記事では、福島県会津若松市(あいづわかまつし)の会州一酒造(かいしゅういちしゅぞう)山口合名会社を特集します。 会津藩御用商人から金賞受賞の酒造りへ ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業は寛永20年(1643)、永年、会津藩の御用商人を担っていました。明治以降も各種の鑑評会、品評会に入っています。 たびたび経営危機の困難を乗り越え、良質な酒造りを心がけています。 昨年、今年は山田錦50% ...
日常に寄り添い人を幸せにする酒づくり 【笹の川】笹の川酒造‐福島県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第267回目の当記事では、福島県郡山市(こおりやまし)の笹の川酒造(ささのかわしゅぞう)を特集します。 猪苗代湖の水と福島県産米で醸す多彩な酒類 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業は1765年(明和2年)。清酒、合成酒、甲類焼酎、乙類焼酎、ウイスキー、スピリッツ、リキュールなどを製造しています。 仕込水は猪苗代湖を水源とする安積疎水を使用し、大吟醸の原料米以外は全て福島県産米を使用しております。 ―代 ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第220回目の当記事では、福島県二本松市(にほんまつし)の大七酒造(だいしちしゅぞう)を特集します。 超扁平精米技術の粋、極上の味わい ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業1752年、大七酒造は生酛造りにおいて、全国随一の評価と実績を誇ります。伊勢国より二本松に来住して始まった歴史は、現当主で十代目を数えます。 独自に開発した超扁平精米技術や無酸素充填システムなど、伝統と革新が相まって、個性豊かな名酒を ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第212回目の当記事では、福島県会津若松市(あいづわかまつし)の宮泉銘醸(みやいずみめいじょう)を特集します。 こだわりと情熱の酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 昭和30年(1955年)に創業し、原料の処理から出荷までの全ての工程においてこだわりを持って酒造りを行っております。皆様に愛される酒を造ることを目指しております。 ―代表銘柄は? 「冩樂 純米酒」 フルーティーな香りがあり、味わいは、米の ...
会津の水を使い、会津の蔵人が醸し出す、正真正銘の会津の酒【末廣】末廣酒造‐福島県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第200回目の当記事では、福島県会津若松市(あいづわかまつし)の末廣酒造(すえひろしゅぞう)を特集します。 受け継がれる山廃の響き、会津の酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 幕末の動乱の足音が響き始めた嘉永3年(1850年)創業。大正時代には山廃の祖、嘉儀金一郎による初めての試醸が行われ、以来その山廃による酒造りは柱の一つになっている。 会津若松の中心部に位置する嘉永蔵の建物は、国の登録有形文化財となっ ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第156回目の当記事では、福島県磐梯町(ばんだいまち)の榮川(えいせん)を特集します。 名水との絆、醸し出すのお酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 明治2年、会津若松市内宮森文次郎酒造店より分家現在地に於て宮森榮四郎酒造店を創業。昭和22年、国税庁から東北で初の一級酒工場の指定を受けた。 戦中戦後の統制下の極端な清酒不足時代に於ても一貫して、優良酒の醸造に専念し消費者に品質で奉仕し今日の基礎を築いた。 ...
地域の色を感じ、お客様の心に寄り添う酒造り【千駒】千駒酒造株式会社-福島県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第29回目の当記事では、福島県白河市(ふくしまけんしらかわし)の千駒酒造(せんこましゅぞう)を特集します。 伝統を守りながら新しい挑戦 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 千駒のある白河市は、福島県の南部に位置し、西に高くそびえる那須連峰を臨む自然豊かな城下町です。かつては各地から沢山の馬喰が集まり、威勢の良い掛け声とともに馬市が賑やかに開催されました。 『千駒』は、若駒の蹄の音とたくましい姿を醸造した酒に ...
様々な醸造の可能性を自由に楽しく突き詰めていく酒造り【生粋左馬】有賀醸造合資会社-福島県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第27回目の当記事では、福島県白河市(ふくしまけんしらかわし)の有賀醸造(ありがじょうぞう)を特集します。 一級河川 阿武隈川の源として那須山系が蓄えた清冽な水で仕込んでいます。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 福島県白河市東地域にある、安永3年(1774年)創業の造り酒屋です。この地域にはかつて越後高田藩(現在の新潟県上越市)の飛び領があり、そこを治める陣屋が当蔵のすぐ裏手にできたことが創業のきっかけ ...
最上の「きれいなあまさ」を目指す酒造り【名倉山、月弓、会津士魂】名倉山酒造株式会社-福島県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第7回目の当記事では、福島県会津若松市(ふくしまけんあいづわかまつし)の名倉山酒造(なぐらやましゅぞう)を特集します。 全国新酒鑑評会で11年連続金賞 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 名倉山は大正7年、今でいうところの酒の鑑定官のような仕事をしていた初代松本善六によって創業。創業当初は「竹正宗」という銘柄で販売されていました。昭和12年頃に猪苗代湖畔にある名倉山の美しさから現在の銘柄である「名倉山」へ変 ...
完全ドメーヌで蒸留する米焼酎【ねっかSpecialEdition、ばがねっか 壱型】合同会社ねっか-福島県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第6回目の当記事では、福島県南会津郡只見町(ふくしまけんみなみあいづぐんただみちょう)の ねっか を特集します。 4人の米農家と、1人の醸造家が立ち上げた、完全ドメーヌの米焼酎蒸留所 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 2016年創業、2017年4月発売に米焼酎の販売を始めた創業5年の、まだ新しい蒸留所になります。只見町は、福島県の西北部。新潟県との県境にある人口4000人の小さな町です。人口は少ないですが ...
茨城県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第283回目の当記事では、茨城県笠間市(かさまし)の須藤本家(すどうほんけ)を特集します。 本流に拘る大門酒造の酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 古くから地域の繁栄と弥栄を念頭に酒造りの本流に拘った酒造りをして参りました。プラットホームは健康です。 ―代表銘柄は? 「純米大吟醸酒 山桜桃 無濾過・生々」 純米大吟醸酒 山桜桃 無濾過・生々 は日本初の生酒です。 Domaine De La Roma ...
いつも誰かの“よろこびごと”に寄り添うお酒を造る 【御慶事】青木酒造‐茨城県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第276回目の当記事では、茨城県古河市(こがし)の青木酒造(あおきしゅぞう)を特集します。 古河の伝統を守り続ける家族経営の酒蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 青木酒造は天保2年(1831年)十一代将軍家斉の時代に、茨城県西部渡良瀬川と利根川の交わる古河に創業しました。 現在では古河唯一の地酒を造る酒蔵として、小規模ながらも家族で営み、代々受け継いできた土地や伝統を守っています。 主要銘柄「御慶事」は ...
百六十余年の歴史とともに、昔ながらの酒蔵を守りながら、挑戦することを忘れない蔵【徳正宗】萩原酒造‐茨城県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第257回目の当記事では、茨城県境町(さかいまち)の萩原酒造(はぎわらしゅぞう)を特集します。 恵まれた利根川流域と歴史が育む酒蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 萩原酒造は茨城県猿島郡境町にあります。境町は、利根川を挟んで千葉県の関宿町(現在・野田市)と対面しており、利根川流域の恵まれた水利を生かして室町時代から交通の要所として栄えました。 弊社が酒造りを始めたのは、安政2年(1855年)初代藤右衛門 ...
結城の気候風土を生かした地酒づくり 【武勇】株式会社武勇‐茨城県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第229回目の当記事では、茨城県結城市(ゆうきし)の武勇(ぶゆう)を特集します。 伏流水の恩恵で育まれる伝統地酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 江戸時代、慶応年間創業。結城の気候風土を生かした昔ながらの地酒づくりを行っている。仕込み水には鬼怒川水系の伏流水を使用。結城は昔から風水害が少なく、地下水が豊富で水質も良く醸造には適した土地である。 同じ町内に酒・味噌・醤油の醸造所が揃っているのも全国では珍し ...
鬼怒川の真水で育てた「辛口の愛娘」【一人娘】山中酒造店‐茨城県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第223回目の当記事では、茨城県常総市(じょうそうし)の山中酒造店(やまなかしゅぞうてん)を特集します。 愛情込めた蔵の酒、幸せの一滴 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 茨城県に位置する当蔵は、関東平野のほぼ中央に位置しています。江戸時代の文化2年(1805年)の蔵火災を創業年とし、その後は口あたりの柔らかな辛口酒を造り続けております。 当蔵では、隣接する鬼怒川の伏流水を使い、苦心の末、独自の二段仕込みを ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第171回目の当記事では、山口県周南市(しゅうなんし)の原田(はらだ)を特集します。 伝統の蔵、復活の醸し手 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業文政2(1819)年創業。山口県東部の瀬戸内海側、徳山駅から徒歩10分という街なかに酒蔵があります。 昭和20年に空襲で酒蔵全焼、昭和60年には自社醸造中止というの困難を切り抜け、平成17年に12代目蔵元原田康宏が自ら杜氏となり20年ぶりに自社醸造を復活しまし ...
「酵母無添加・完全発酵にこだわる旨い酒を求め」【米宗】青木酒造‐愛知県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第170回目の当記事では、愛知県愛西市(あいさいし)の米宗(こめそう)を特集します。 味のある旨い酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1805年創業。1959年伊勢湾台風により全壊。以後、山廃造りに注力し「味のある旨い酒造り」を志す。 今では生酛山廃造り中心に酵母無添加・完全発酵を主に米宗にしかない旨い味を日々追求しております。 ―代表銘柄は? 代表銘柄は「米宗 山廃純米」です。 山廃仕込でがっつり ...
「関東の米どころの真ん中にある小さな酒蔵」【京の夢】竹村酒造店‐茨城県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第169回目の当記事では、茨城県常総市(じょうそうし)の京の夢(きょうのゆめ)を特集します。 270年の歴史を刻む近江商人の酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 滋賀県から出てまいりました近江商人が、地の利を生かした清酒醸造(天満屋)を営んでおりました。それが私どもの270年の歴史の始まりです。 最初は現在の常総市本石下町(現・石下中央公民館)に本店(醸造蔵)を置き、水海道・藤代・大阪など数か所に支 ...
飲んで食べて健康に、エキサイティングな酒蔵【紬美人】野村醸造-茨城県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第114回目の当記事では、茨城県常総市(いばらきけんじょうそうし)の野村醸造(のむらじょうぞう)株式会社を特集します。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 野村醸造は明治30年に創業しました。関東平野の北端、茨城県常総市にて124年に渡り酒造りに励み現社長で五代目になります。 10年前に関東東北地震で蔵の一部が損壊、5年前には鬼怒川の洪水により、1.5Mまで冠水し大きな打撃を受けました。洪水からの再建には地 ...
永きにわたり飲み続けてもらえる酒づくり【白菊】廣瀬商店-茨城県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第91回目の当記事では、茨城県石岡市(いばらきけんいしおかし)の合資会社廣瀬(ひろせ)商店を特集します。 創業から200年に渡って地域の皆様に愛されてきた廣瀬商店 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 霞ヶ浦にそそぐ恋瀬川のほとり、西に筑波山を望む高浜の地に廣瀬商店は文化二年(一八〇五年)創業しました。酒造りに適した寒冷な土地と、筑波山水系の良質な地下水に恵まれ、永く二〇〇年に渡って地域の皆様から愛されて参り ...
群馬県
川場村の自然美を日本酒で表現する蔵 【 水芭蕉 】群馬県-永井酒造
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第126回目の当記事では、群馬県利根郡(とねぐん)の永井酒造(ながい)を特集します。 自然美を表現する綺麗な酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業1886年。利根川源流域に位置する群馬県川場村で「自然美を表現する綺麗な酒造り」をモットーに“水芭蕉”と“谷川岳”の2銘柄を醸す酒蔵です。 「伝統と革新」をテーマに、スパークリング、スティル、ヴィンテージ、デザートという4種類の日本酒を食事のコースに合わ ...
ブルゴーニュボトルにボトリング!イエローゴールドのヴィンテージ日本酒SAKAEMASU【SAKAEMASU、KIYOMIZU】清水屋酒造-群馬県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第97回目の当記事では、群馬県館林市(ぐんまけんたてばやしし)の清水屋酒造(しみずやしゅぞう)有限会社を特集します。 新潟県から始まった歴史をもつSAKAEMASU ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 SAKAEMASU(榮万寿)の歴史は、実は新潟県から始まります。酒造りを始めた初代が、新潟から美味しい水にこだわり辿り着いたのが、ここ「群馬県館林市(旧館林町)」でした。1873年(明治6年)に創業し、一時は ...
手間を惜しまず丁寧に時代に順応した日本酒を醸す【流輝(るか)、平井城】松屋酒造-群馬県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第87回目の当記事では、群馬県藤岡市(ぐんまけんふじおかし)の松屋酒造(まつやしゅぞう)株式会社を特集します。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 明治後期より富山県で米問屋を営んでおりましたが、日本酒を造るようになりました。 1951年現在の群馬県藤岡市に引っ越してきて松屋酒造株式会社を立ち上げました。 ―代表銘柄は? 流輝(るか)、平井城です。 海のない群馬県では贅沢な新鮮な魚との味わいを楽しんでほしい ...
埼玉県
全量を特異な石灰岩系硬水で醸す金賞常連蔵 【帝松】松岡醸造‐埼玉県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第277回目の当記事では、埼玉県比企郡(ひきぐん)の松岡醸造(まつおかじょうぞう)を特集します。 松岡祐右ヱ門が築いた伝統の酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 元々は新潟、越後頸城郡柿崎で酒造りにかかわる家柄に生まれた初代・松岡祐右ヱ門。 1851年(江戸時代:嘉永四年)に水・米・消費・物流など、酒造りに適した環境である埼玉県小川町にて創業。現在に至る。 ―代表銘柄は? 「帝松」 帝は国の頂点を指し ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第246回目の当記事では、埼玉県秩父市(ちちぶし)の矢尾本店(やおほんてん)を特集します。 古きを重んじながら新たなステップへと突き進む ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 寛延2年創業。滋賀県近江市(近江商人)より秩父の地へやってきて今年で275年。 初代の矢尾利兵衛から始まり現在の木村直之杜氏に継承され白梅→花陽→そして現在の秩父錦へと銘柄も変わって行きました。 杜氏は昭和頃、越後杜氏から始まり南部杜氏 ...
埼玉の酒造好適米「さけ武蔵」を中心にした酒造り【琵琶のささ浪】麻原酒造‐埼玉県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第243回目の当記事では、埼玉県入間郡(いるまぐん)の麻原酒造(あさはらしゅぞう)を特集します。 人から人へ、さゝ浪の如く ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 初代麻原善次郎は琵琶湖の畔に生まれ、九歳にて東京青梅の酒蔵へ奉公に入り、明治15年、二十九歳の時、毛呂山にて開業するに至りました。現社長で五代目となります。 ―代表銘柄は? 「琵琶のささ浪」 『近江やに名高き松の一本木 先から先へと開くさゝ浪浪』 心 ...
清酒造りだけではない、あらゆるジャンルを製造する総合アルコール飲料メーカー【晴菊】東亜酒造‐埼玉県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第215回目の当記事では、埼玉県羽生市(はにゅうし)の東亜酒造(とうあしゅぞう)を特集します。 多彩な味わい、東亜酒造のアルコール製品 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 東亜酒造は、1625年に秩父で酒造りを開始。1941年に穀倉地帯の羽生市に本社を移し、現在まで400年近い歴史を歩んで参りました。主力製品の清酒は「晴菊」をメインブランドとし、リキュール、ウイスキーなど多種多様な製品を製造・販売しておりま ...
埼玉県なのに「日本橋」を造り続けて200余年【日本橋】横田酒造‐埼玉県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第197回目の当記事では、埼玉県行田市(ぎょうだし)の横田酒造(よこたしゅぞう)を特集します。 初心忘れずの酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 文化2年(1805年)創業。初代横田庄右衛門は、滋賀県出身の近江商人。江戸の商圏で一旗上げるため、関東近郊の水の良い土地を選び、酒蔵を建てる。 酒銘「日本橋」の由来は、創業者がお江戸日本橋の酒問屋で修業の後、独立する際、「初心忘れるべからず」との家訓を込めて ...
「伝統の技と新しい技術のFUSION」【天覧山・五十嵐】五十嵐酒造‐埼玉県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第161回目の当記事では、埼玉県飯能市の天覧山(てんらんざん)を特集します。 緑豊かな地で生まれた淡麗な味わい ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業者である五十嵐久蔵氏は、もともとは他社の杜氏を務めていましたが、独自の酒造りをめざして明治30年(1897年)に独立。緑豊かな飯能の地で日本酒を造り始めたのが、五十嵐酒造の始まりです。 弊社が基本とするのは、飯能の自然の恵みを活かした酒造り。名栗川と成木川と ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第122回目の当記事では、埼玉県深谷市(ふかやし)の滝澤酒造(たきざわ)株式会社を特集します。 「和醸良酒」を心がけ、丁寧な酒造りを行う「滝澤酒造」 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 滝澤酒造は、文久三年(1863年)に埼玉県の小川町で創業。明治三十三年(1900年)に現在の深谷市に蔵を構えました。米の蒸し、麹造り、もろみの仕込みなど昔ながらの道具を用い、伝統的な酒造りを継承しています。 和は良酒を醸し、 ...
若い蔵人たちによる伝統と革新の酒造り【越生梅林、中田屋】佐藤酒造店-埼玉県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第96回目の当記事では、埼玉県入間郡(さいたまけんいるまぐん)の有限会社佐藤酒造店(さとうしゅぞうてん)を特集します。 ふくらみがあり後味の軽い酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1844年創業。秩父山地の東に位置する人口一万人あまりの越生町。酒蔵の近くには関東三大梅林のひとつに数えられる越生梅林があり、裏手には黒山三滝を源とする越辺川の清流が流れています。 酒造りにはその清麗で柔らかな水質の伏流水を使 ...
埼⽟の酒⽶、さけ武蔵で仕込んだこだわりの⽇本酒「⻑瀞」【⻑瀞】藤﨑摠兵衛商店-埼玉県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第85回目の当記事では、埼玉県秩父郡(さいたまけんちちぶぐん)の株式会社藤﨑摠兵衛商店(ふじさきそうべえしょうてん)を特集します。 埼⽟でしか造れない地酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業享保十三年(1728年)。埼⽟の地で⽇本酒を世に広めることに尽力した近江商人十一屋・藤﨑摠兵衛の志を継ぐ⽇本酒蔵です。 平成三十年(2018年)9月。十一屋・藤﨑の伝統である「技で磨き、⼼で醸す」酒造りを深める ...
栃木県
驚きを与え続ける独創的な酒造り。挑戦を続ける国登録有形文化財指定の酒蔵 【門外不出、若盛】西堀酒造‐栃木県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第284回目の当記事では、栃木県小山市(おやまし)の西堀酒造(にしぼりしゅぞう)を特集します。 日光街道沿いに位置する国登録有形文化財指定の酒蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 明治5年(1872)創業、栃木県小山市の国登録有形文化財指定の酒蔵。代表銘柄「門外不出」は、今でも9割以上が栃木県内で消費される少量生産の栃木の地酒。 国内外の複数の受賞歴が示す確固たる技術を基に、伝統製法を守る“継承”タイプの ...
珍しい有機日本酒と蜂蜜酒を栃木の小さな田舎から 【天鷹】天鷹酒造‐栃木県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第266回目の当記事では、栃木県大田原市(おおたわらし)の天鷹酒造(てんたかしゅぞう)を特集します。 天鷹の安心・安全・楽しい酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 「辛口でなければ、酒ではない」と辛口に拘り、1914年の創業以来、辛口酒のみを造り続けています。 また近年、全国でも珍しい有機の日本酒を造り始めました。皆様へ「安心・安全・楽しい」商品をお届けするため、天鷹は常に高品質のものを造り続けていま ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第217回目の当記事では、栃木県栃木市(とちぎし)の相良酒造(さがらしゅぞう)を特集します。 栃木地元の恵みを味わう純米酒の極み ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 天保2年(1831年)、酒造りに理想的な水を探し求めた初代により、日光連山からの伏流水が自噴する現在の地にて酒造りを始める。屋号「清水屋」からは仕込水へのこだわりと自信を感じさせられる。 かつては越後杜氏を招聘していたが現在は蔵元杜氏による酒造 ...
「地の酒に生きる、栃木の地酒「惣誉」」【惣誉】惣誉酒造‐栃木県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第175回目の当記事では、栃木県芳賀郡(はがぐん)の惣誉酒造(そうほまれ)を特集します。 卓越した酒質の地酒、栃木の誇り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 明治5年創業。栃木の地酒「惣誉」です。蔵は栃木県の東部に位置し、鬼怒川水系の伏流水を仕込みに使用しています。 国内向けの全出荷量のうち9割程度が栃木県内向けの、まさに地酒蔵です。2001年から生酛仕込を復活させて取り組んでいます。惣誉の生酛は、軽やかな ...
「 稀有な湧水を使いこなし瑞々しい酒質を長期に保つ酒を実現」【松の寿】松井酒造店‐栃木県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第160回目の当記事では、栃木県塩谷郡塩谷町の松の寿(まつのことぶき)を特集します。 超軟水が紡ぐ繊細な風味、限られた流通量 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1865年、初代松井九朗治が新潟から水を求め栃木で酒蔵を創業。 現在五代目蔵元が自ら杜氏とし酒造りをしています。限られた設備の中、国内外の酒コンペで数々の賞を受賞。仕込み水として使用するのは自社裏山から湧き出す超軟水。 発酵力が弱く酒造りには技術が ...
まごころ一献。旨い酒は、蔵人の心意気が造る【四季桜】宇都宮酒造‐栃木県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第140回目の当記事では、栃木県宇都宮市(うつのみやし)の宇都宮酒造(うつのみやしゅぞう)を特集します。 日本酒造りの技を受け継ぎ、旨い酒を追求し続ける ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 明治4年(1871年)栃木県河内郡平石村柳田に初代・今井翠吉が今井酒造店を創業。第二次世界大戦時、物資統制令により休業。昭和22年復活しました。 創業当初は「四季の友」と銘していたが、初代が詠んだ「月雪の友は他になし四季 ...
「酒造り」は「米作り」から、創業以来340余年田んぼと共に歩む酒蔵 【開華】第一酒造‐栃木県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第135回目の当記事では、栃木県佐野市(さのし)の第一酒造を特集します。 「品質第一」にこだわった酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 第一酒造は、栃木県で最も歴史のある1673年(延宝元年)の創業以来、「品質第一」を社訓とし、米、水、手造りにこだわった酒造りを、340余年変わらず続けてきた造り酒屋です。 創業の1673年は、徳川四代将軍家綱の時代、その当時、佐野のお酒は、渡良瀬川から利根川、江戸川へ ...
東京都
SAKEの可能性を広げる、東京八王子クラフト 【prototype】東京八王子酒造‐東京都
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第270回目の当記事では、東京都八王子市(はちおうじし)の東京八王子酒造(はちおうじしゅぞう)を特集します。 黒塀通りの新たな醸造所 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 2023年6月開業。東京で令和初、10番目の酒蔵です。 かつて宿場町として栄えた東京、八王子。その面影を残す黒塀通りの一角に私たちの醸造所はあります。 八王子駅から徒歩5分、料亭「すゞ香」に併設するコンパクトな醸造所ながら充実した設備環境の ...
東京島酒が地理的表示(GI)に指定されました!「GI東京島酒」
2024年(令和6年)3月 13日、地域の⾵⼟と結びついた特産品を保護する国の制度「地理的表示(GI)」に、伊豆諸島を産地とする焼酎の「東京島酒」が国税庁長官より指定されました。焼酎のGI指定は平成17年以来の18年ぶりで、日本では、「壱岐焼酎」「球磨焼酎」「薩摩焼酎」「琉球泡盛」に次ぎ5件目となります。 東京の島々を球体に重ね合わせ、GIを構成した東京の島の結束を表したシンボル GI東京島酒とは ⑴ 原料の特徴伊豆諸島で製造される東京島酒には、3つのタイプがあります。 1.「麦こうじを使用した芋焼酎」2 ...
「200周年を祝う進取の精神と伝統の融合-東京銘酒」【嘉泉】田村酒造場‐東京都
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第158回目の当記事では、東京都福生市の嘉泉(かせん)を特集します。 歴史と共に織りなす土蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 文政五年創業(1822年)明治時代中期まで続いた店蔵(たなぐら)制度では、近隣の24の酒蔵の経営、製造などを監督役(総本店) を務めた酒蔵でございます。 ―代表銘柄は? 代表銘柄は「特別本醸造 幻の酒 」です。 酒造好適米を60%まで精米した特別本醸造酒。旨口にして、味のふくらみ ...
大正4年創業・八丈島最古の焼酎蔵【江戸酎】八丈島酒造-東京都
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第78回目の当記事では、東京都八丈島(とうきょうとはちじょうじま)の八丈島酒造(はちじょうじましゅぞう)合名会社を特集します。 大正4年創業の現在100年以上になる焼酎の蔵元 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 大正4年創業の現在100年以上になる焼酎の蔵元です。現在杜氏は3代目で、4代目とともに焼酎造りに励んでおります。 八丈島の焼酎の歴史は、1606年に最初の流罪人が流され、1881年に全員放免になるま ...
神奈川県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第262回目の当記事では、神奈川県相模原市(さがみはらし)の久保田酒造(くぼたしゅぞう)を特集します。 丹沢山系の清らかな水が育む伝統の味わい ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業1844年(弘化元年)、丹沢山系の湧水を用いて日本酒・本格焼酎・梅酒「相模灘」の製造を行っています。 ―代表銘柄は? 「相模灘 純米吟醸 美山錦」 長野産美山錦を50%まで磨き上げて仕込んだ純米吟醸。繊細な美山錦の特性を生かす ...
時間に寄り添う日本酒 HINEMOS【HINEMOS】RiceWine‐神奈川県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第258回目の当記事では、神奈川県小田原市(おだわらし)のRiceWine(ライスワイン)を特集します。 時間に寄り添う日本酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 HINEMOS(ひねもす)は時間をコンセプトにした日本酒ブランド。もっと日本酒を日常の一つひとつの時間に寄り添う身近なものにしたいという想いから、世界中の人たちの共通概念である「時間」を商品コンセプトにしました。 創業300年以上続く「森山酒造」 ...
和食のおいしさを引き立て、飲み飽きしない純米燗酒を醸す【丹沢山】川西屋酒造店‐神奈川県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第143回目の当記事では、神奈川県足柄上郡(あしがらかみぐん)の丹沢山(たんざわさん)を特集します。 伝統を守りつつ、全量純米蔵に。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 元々の当主は南足柄において米穀商などの事業を営んでいたが、明治30年に南足柄から酒匂川を渡り、現在の山北町にあった造り酒屋を居抜きで買い取り、酒造業を始めた。 川の西側に位置することから社名を「川西屋酒造店」とした。1986年、「丹沢山」の ...
令和3年 神奈川県で唯一の全国新酒鑑評会 金賞受賞蔵【盛升(さかります)】黄金井酒造-神奈川県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第113回目の当記事では、神奈川県厚木市(かながわけんあつぎし)の黄金井酒造(こがねいしゅぞう)株式会社を特集します。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 黄金井酒造は創業1818年、神奈川県厚木市唯一の造り酒屋で、東丹沢の自然豊かな地に蔵を構えています。周辺には七沢温泉、地豆腐屋があり、水に恵まれた地域でもあります。軟水で仕込んだ清酒「盛升」は、口あたりがまろやかで後切れのよい食中酒向きの酒質が特長です。 ...
梅の里に息づく、真心と誠意をこめた酒造り【曽我の誉、箱根街道、曽我梅林の梅酒 】石井醸造-神奈川県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第102回目の当記事では、神奈川県足柄上郡(かながわけんあしがらかみぐん)の石井醸造(いしいじょうぞう)株式会社を特集します。 気候温暖・風光明媚な地で行雲流水綿々と酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 「一輪の梅の香りや 酒の味」 私ども「曽我の誉」は神奈川・小田原名産である梅干の産地・曽我梅林にほど近く、気候温暖・風光明媚(ふうこうめいび)な地で行雲流水綿々と酒造りを行っております。 頭書の句は梅 ...
神奈川の屋根丹沢の懐、全国銘水100撰の地、秦野より音楽を聴いたお酒を【白笹鼓、笹の露、モーツァルト】金井酒造店-神奈川
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第83回目の当記事では、神奈川県秦野市(かながわけんはだのし)の株式会社金井酒造店(かねいしゅぞうてん)を特集します。 従来の酒造りを一新 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 明治元年(1868年)に創業しました。 四代目蔵元佐野秀郎は、従来の酒造りを一新すべく、杉山晋朔氏(東大醸造学教授)の指導のもと杜氏に越後杜氏木曽久平を起用、現金井酒造店の礎を築き、人々が商売繁盛や豊作を祈願した「白笹稲荷」にちなんだ ...
自家醸造再開4年目の地方創生を目指す酒蔵 【酒田錦、セトイチ、あしがり郷】瀬戸酒造店 -神奈川県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第55回目の当記事では、神奈川県足柄上郡 (あしがらかみぐん)の 株式会社瀬戸酒造店 (せとしゅぞうてん)を特集します。 地域を活性化するために再始動した酒蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 慶応元年(1865年)創業、1980年から2018年までの38年間、自家醸造を休止していましたが、地域を活性化するために再始動した酒蔵です。 丹沢山(たんざわさん)と富士山の伏流水(ふくりゅうすい)を使い、全量小仕 ...
新潟県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第280回目の当記事では、新潟県上越市(じょうえつし)の妙高酒造(みょうこうしゅぞう)を特集します。 頚城平野に根付く200年の伝統と革新 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 標高2454m越後富士とも言われる秀峰『妙高山』が見下ろす新潟県の中でも有数の米処頚城平野に蔵は有ります。 創業は1815年、清らかな水と上質な米、酒造りに最高に適した土地で200年以上の伝統を守りながらも革新的な酒造りにも挑戦し続け ...
創業二百年以上の伝統を守り老舗ならではの酒を醸します【王紋】王紋酒造‐新潟県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第274回目の当記事では、新潟県新発田市(しばたし)の王紋酒造(おうもんしゅぞう)を特集します。 新発田藩と市島家の420年 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 当蔵の総本家「市島家」は、約420年前の慶長3年(1598年)に、加賀大聖寺より越後新発田藩に移封された溝口侯に随伴して当地に移住しました。 市島家は薬種問屋を始め、酒造、金融、回船業などで商業資本を蓄積する一方、沼澤の多い荒蕪の土地を意欲的に開拓 ...
やわらかな軟水の湧き水仕込みを活かした酒造り【鮎正宗】鮎正宗酒造‐新潟県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第263回目の当記事では、新潟県妙高市(みょうこうし)の鮎正宗酒造(あゆまさむねしゅぞう)を特集します。 明治から続く湧き水が生み出す逸品 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業は、明治8年(1875年)。初代が枯渇することを知らない良質の湧き水で酒を醸したことが始まりです。 酒の原料となる湧き水は、今も蔵の下からこんこんと湧き出ており、毎時6トンの水量を誇ります。蔵元に寄り添う山の地下深くより自然に湧き ...
安らぎと喜びと感動を伝える酒造り 【越の白鳥】新潟第一酒造‐新潟県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第260回目の当記事では、新潟県上越市(じょうえつし)の新潟第一酒造(にいがただいいちしゅぞう)を特集します。 4軒の酒蔵の結集から生まれた蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1922年亀屋酒造として創業。1963年に5軒の酒蔵が合併して新潟第一酒造株式会社に改組。 農学博士の飯田茂次先生を招致し、裏山からこんこんと湧く柔らかい伏流水で、当初はすっきり綺麗な辛口酒を目指した。 ―代表銘柄は? 「純米吟醸 ...
「醸道無限」二百余年の拘りが極上の酒を醸し出す、淡麗旨口【〆張鶴】宮尾酒造‐新潟県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第253回目の当記事では、新潟県村上市(むらかみし)の宮尾酒造(みやおしゅぞう)を特集します。 良質な素材と歴史ある酒造技術 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業1819年、新潟の県北に蔵を構え、鮭の遡上で知られる三面川の源流となる朝日連峰からの超軟水の伏流水を仕込みに使い、日本一の米処新潟で育まれた良質の酒米を自社精米工場にて磨き上げます。 宮尾家には2代目当主が酒造技術を記した「酒造伝授秘法の巻」が ...
辛口の多い新潟県では異色ともいえる旨口に拘る酒蔵 【天神囃子】魚沼酒造‐新潟県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第241回目の当記事では、新潟県十日町市(とおかまちし)の魚沼酒造(うおぬましゅぞう)を特集します。 清らかな信濃川と共に紡ぐ、十日町の伝統酒蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 当蔵は1873年創業、1916年から会社組織になりました。十日町市の山際に位置し、新潟県の酒造好適米を信濃川の伏流水で仕込んでおります。 この地方に伝わる神事唄「天神囃子」を銘柄に冠しております。 ―代表銘柄は? 「特別純米酒 ...
小さな蔵の大きな夢、日本一の酒造り【かたふね】竹田酒造店‐新潟県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第239回目の当記事では、新潟県上越市(じょうえつし)の竹田酒造店(たけだしゅぞうてん)を特集します。 砂丘が生んだ芳醇旨口のお酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業1866年。創業150年を超える新潟県上越市にあります。 私たちの蔵は、海岸線のほど近くにあり、砂丘の上に経っています。その砂丘の中を、何年も何年もかけて濾過された水で醸す酒は、米の甘い香り、ふくよかな味わいを蓄えます。地下を通った水で醸 ...
北越後 新発田にある日本初のアルミ缶入り生原酒を発売した蔵【菊水】菊水酒造‐新潟県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第232回目の当記事では、新潟県新発田市(しばたし)の菊水酒造(きくすいしゅぞう)を特集します。 伝統と発酵の力で織りなす酒蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業1881(明治14)年。越後平野の北部に位置する新潟県新発田市の酒蔵です。創業以来培ってきた発酵の力で大地の恵みを醸しながら営々と受け継がれてきた日本の文化を生かし、人々の健康、憩い、楽しみに貢献してまいります。 ―代表銘柄は? 「菊水ふなぐ ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第225回目の当記事では、新潟県長岡市(ながおかし)の恩田酒造(おんだしゅぞう)を特集します。 越後山脈の恵み、自社栽培の一本〆-長岡の銘酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業は明治8年(1875年)、長岡市の南端、六日市町にあり古くは古志郡の中心地でしたが、昭和29年(1954年)長岡市と合併。越後山脈の麓に位置し、豊富な地下水と周囲の自社田を利用した「一本〆」を栽培し、酒造りを行っています。 ―代 ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第216回目の当記事では、新潟県新潟市(にいがたし)のDHC酒造を特集します。 安心のコーシャ認証、DHC酒造の品質保証 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 DHC酒造は、新潟市北区(旧豊栄市)の地で100年以上に渡り日本酒を造りつづけてきた酒蔵です。2014年にDHCグループの一員となりDHC酒造と生まれ変わりました。 食の安全性を保証する制度として、約450年の歴史を誇る「コーシャ」認証取得など、創業明 ...
石川県
侍魂平家の末裔が醸す全量槽搾りの小さな加賀の酒蔵【十代目】橋本酒造‐石川県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第261回目の当記事では、石川県加賀市(かがし)の橋本酒造(はしもとしゅぞう)を特集します。 侍の誇り、侍の酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業宝暦十年、西暦1760年、以来264年、日本の伝統文化である日本酒を醸し続けているという誇りを胸に、日々精進しております。 歴史をひも解きますと、私たちの先祖は平家の侍であります。そう、私たちのお酒はまさに侍が創り出したお酒です。 このお酒には、日本の侍魂が ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第174回目の当記事では、石川県白山市(はくさんし)の菊姫(きくひめ)を特集します。 霊峰白山の滴から生まれる加賀の菊酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 霊峰白山の頂から流れだす雪解け水が、やがて川となり麓の地を潤します。その滴りから醸し出される芳醇な美酒は、古来より「加賀の菊酒」と呼ばれ賞賛されてきました。 「太閤記」には、豊臣秀吉が醍醐の花見に取り寄せたことが記されています。 菊姫は、天正年間(15 ...
創業四百三十余年の歴史を誇る城下町「金沢」加賀藩の酒蔵【加賀鶴】やちや酒造-石川県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第64回目の当記事では、石川県金沢市(いしかわけんかなざわし)のやちや酒造株式会社を特集します。 前田利家公専用の酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 本能寺の変の翌年(天正11年)に前田利家(まえだとしいえ)公専用の酒造りのため、神谷内屋仁右衛門(かみやちや じんうえもん)が尾張の国から金沢へ移住したのが始まりの城下町「金沢」にある加賀藩の酒蔵です。 前田家三代利常(としつね)公から神谷内屋の神を外 ...
福井県
テロワールにこだわった酒造り 【鬼作左袋吊り搾り】久保田酒造‐福井県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第268回目の当記事では、福井県坂井市(さかいし)の久保田酒造(くぼたしゅぞう)を特集します。 福井県丸岡町で伝説の酒『越前豊原の酒』を紡ぐ270年 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 わたしたちは福井県の小さな町で270年余り酒造りに携わってきました。はじまりは宝暦3年。「失われた室町時代 伝説の酒『越前豊原の酒』をふたたび」。当時の越前丸岡藩主から久保田家に下された命でした。酒造りは、この地とともに喜び ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第191回目の当記事では、福井県大野市(おおのし)の南部酒造場(なんぶしゅぞうじょう)を特集します。 奥越前で生まれた、手造りのお酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 北陸の小京都、奥越前と呼ばれる大野市で、当社は1733年に創業いたしました。 雪深く寒冷な気候、名水百選に選ばれし清水に恵まれ、高品質な酒米の名産地として名高いこの地で、私たちは原材料にこだわり、手造りで、目の届く範囲の量を丁寧に醸すことを ...
福井県で1番小さな酒蔵が醸す、スッキリな喉越しとエロスな日本酒を表現 【越の鷹】伊藤酒造-福井県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第124回目の当記事では、福井県福井市(ふくいし)の伊藤酒造(いとうしゅぞう)合資会社を特集します。 蔵元自身が満足できる「純米吟醸」を常に探求・醸造にチャレンジいたしている ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 福井藩の菩提寺「大安禅寺」ちかく九頭龍川近くに蔵がたっております。明治から大正の時代醸造しました日本酒を川から三国湾まで川船で運び、そこから京都や新潟など運輸業も合せて営んできました。 時代が流れ交 ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第121回目の当記事では、福井県福井市(ふくいけんふくいし)の力泉酒造(りきせんしゅぞう)有限会社を特集します。 のどかな田舎町にある創業110年を超える力泉酒造 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 当社は1904年創業で、現在5代目です。場所は、福井市中心部から10kmほど海に向かったところにある、のどかな田舎町です。 秋には東京ドーム約4個分の広さのコスモスが咲き乱れるコスモス公園があります。また、海が ...
「味わう」という一瞬に、知恵を絞る。【黒龍、九頭龍】黒龍酒造-福井県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第115回目の当記事では、福井県吉田郡(ふくいけんよしだぐん)の黒龍酒造(こくりゅうしゅぞう)株式会社を特集します。 蔵の地下深くから汲み上げた清澄な雪解け水を仕込水として使用 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業1804年(文化元年)、初代蔵元 石田屋二左衛門が永平寺町松岡に創業以来、黒龍酒造ならではの酒造りを追求して参りました。 水質に優れた土地柄や松岡藩が奨励したこともあり、今では黒龍酒造と、他一 ...
福井を代表する酒を目指して、新しい味と、忘れられない味と香りを大切に。お食事と共にある日本酒【若鹿、北の庄、富成喜】舟木酒造‐福井県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第109回目の当記事では、福井県福井市(ふくいけんふくいし)の舟木酒造(ふなきしゅぞう)合資会社を特集します。 戦国時代の朝倉氏ゆかりの名水と言われる岡の泉 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 慶応2年(1866年)創業。代々三右衛門を襲名しました。福井市北東部に位置し霊峰白山を源流とする清冽な良水があり、空気のきれいな田園地帯です。 また近くには戦国時代の朝倉氏ゆかりの名水と言われる岡の泉があり、都市景観 ...
山廃仕込にこだわりつつ、新たな挑戦をする酒蔵【福千歳】田嶋酒造-福井県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第105回目の当記事では、福井県福井市(ふくいけんふくいし)の田嶋酒造(たじましゅぞう)株式会社を特集します。 良質な水が豊かに出る地 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1849年創業。当時は「加茂の井(かものい)」という銘柄で日本酒を造っておりました。 しかし、その地で幾度となく起こる水害によって困り果てた先々代は、良質な水が豊かに出るこの地(現在の蔵がある)で酒造りすることを決意しました。(1953年 ...
日本の伝統的な酒造りを革新する父と息子【真名鶴】真名鶴酒造-福井県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第88回目の当記事では、福井県大野市(ふくいけんおおのし)の真名鶴酒造(まなつる)合資会社を特集します。 特産の酒造好適米や名水百選と雪深い厳寒な気候で行う新しい味わいの酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 真名鶴酒造は、北陸の小京都「越前大野」で宝暦年間(江戸時代中期)より続く老舗の蔵元です。 越前大野は、特産の酒造好適米「五百万石」や名水百選「御清水」さらに雪深く厳寒な気候とも相まって「神が酒造り ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第60回目の当記事では、福井県鯖江市(ふくいけんさばえし)の豊酒造(ゆたかしゅぞう)株式会社を特集します。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 当蔵は、宝暦三年(1753年)豊村野田の地に創業し、地元の皆様に愛飲していただける清酒を造り続けてまいりました。 米・水(日野川伏流水)にめぐまれ、歴代蔵元が酒造りに精進し、高品質の清酒を届けてきたと自負しております。 平成14年の仕込みより、福井県の気候風土が生み ...
福井の風土に寄り添い、伝統と新しい感性を融合させた酒造り【越前岬、優勝】田辺酒造-福井県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第53回目の当記事では、福井県永平寺町(ふくいけんえいへいじちょう)の田辺酒造(たなべしゅぞう)有限会社を特集します。 柔らかな飲み口と骨格のある米由来の旨みを引き出せるよう酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 曹洞宗大本山「永平寺」のお膝元永平寺町で、明治32年より酒造りを行っています。町内には、「清流の町」の象徴である霊峰白山を源とする九頭竜川が流れ、夏は鮎釣り、冬はサクラマス釣りで賑わいます。そ ...
山梨県
創業360年以上の歴史を持ち”山梨の酒街道”の入り口に位置する老舗酒蔵【笹一】笹一酒造‐山梨県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第233回目の当記事では、山梨県大月市(おおつきし)の笹一酒造(ささいちしゅぞう)を特集します。 富士山の恵み、追い求める日本最高の味わい ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 笹一酒造株式会社は山梨県の酒街道の入り口である大月市に位置し、1661年寛文元年に花田屋として創業、1919年に現在の笹一酒造と改名して統合した三百有余年の歴史を持つ会社です。 「笹一」は日本酒の意で使われた「笹」の字と、日本一の富士 ...
八ヶ岳の湧水で醸す!花酵母で楽しむ日本酒と焼酎 【青煌】武の井酒造‐山梨県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第228回目の当記事では、山梨県北杜市(ほくとし)の武の井酒造(たけのいしゅぞう)を特集します。 山梨北杜の酒蔵、地元味わいの革新 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業1865年。江戸末期から続く弊蔵は山梨県最北の北杜市に構えています。2000年代前半まで普通酒中心だった蔵は、2007年に純米ブランド【青煌saykoh】をリリースしてから次々と特定名称酒の拡充に力を入れ、その飲み易さから日本酒初心者を始 ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第164回目の当記事では、山梨県北杜市の七賢(しちけん)を特集します。 300年の歴史を誇る、白州の水の酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業1750年(江戸寛永3年)、300年近い歴史を誇る七賢は、山梨県の日本アルプスの中でも非常に良質な水が湧き出ることで知られた白州エリアに蔵を構えます。 「地元白州の水を体現できる酒」を哲学とし、白州の水と相性の良い造りを追求して吟醸造りの原酒仕立て手法を確立 ...
富士山伏流水で醸す飲み飽きしない酒造り【甲斐の開運、北麓、冨麓、雪解流、大雄峰】井出醸造店-山梨県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第79回目の当記事では、山梨県南都留郡(やまなしけんみなみつるぐん)の井出醸造店(いでじょうぞうてん)を特集します。 冷涼な富士北麓の気候と、豊かな清冽な水でつくる清酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 「甲斐の開運」醸造元井出醸造店は江戸中期(1700年頃)に始めた醤油醸造が前身です。江戸末期(1850年頃)に、当家十六代の井出與五右衞門が、標高850mの冷涼な富士北麓の気候と、豊かな清冽な水に着目し、 ...
長野県
大自然に囲まれ、極寒の季節にお酒を醸す。信州佐久の自然そのものが酒蔵【千曲錦】千曲錦酒造‐長野県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第244回目の当記事では、長野県佐久市(さくし)の千曲錦酒造(ちくまにしきしゅぞう)を特集します。 信州の大自然×蔵人の情熱 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業天和元年(1681年)創業の後宿場町岩村田宿で酒蔵として栄え、約340年という永き年月を刻み続けてきました。 信州の名水、浅間山天然伏流水で仕込まれた、地元で愛されている日本酒です。 ―代表銘柄は? 「千曲錦 大吟醸 酒の精」酒造好適米「山田錦 ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第224回目の当記事では、長野県岡谷市(おかやし)の髙天酒造(こうてん)を特集します。 銘醸地の誇り、信州の老舗 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 明治4年、現在地で初代髙橋巳喜之助によって創業されました。昭和3年には、全国清酒品評会において、清酒「髙天」が長野県初の名誉賞を受賞し、信州清酒の評価を高め、銘醸地として全国に認められる基を築きました。当蔵は「信州の老舗」にも認定されています。 また、当蔵の銘 ...
慶応3年創業。150年の歴史 伝統と精神を引き継ぎ、新たな日本酒への挑戦 【山三、真田六文銭】山三酒造‐長野県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第219回目の当記事では、長野県上田市(うえだし)の山三酒造(やまさんしゅぞう)を特集します。 山三酒造、歴史の輝きを新たに。信州上田の魅力、再び蘇る ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1867 年(慶応3年)創業の山三酒造は、長野県上田市に位置し、東には浅間山や菅平、南には八ヶ岳や蓼科、霧ヶ峰、美ヶ原を擁し、四方を山に囲まれ美しい水に恵まれた環境にある日本酒の酒蔵です。 信州上田の真田家の家紋『真田六文 ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第182回目の当記事では、長野県須坂市(すざかし)の遠藤酒造場を(えんどうしゅぞうば)特集します。 創業から続く真摯なる醸造 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業1864年(元治元年)。信州須坂で初代遠藤徳三郎が地元の皆様に旨し酒を飲んでいただきたいという初心で酒蔵を始めました。 以来、古き伝統を守りながらも新しい技術を取り入れ数々の人気商品を生み出しております。 銘柄は【渓流】【彗】【直虎】などをもち ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第163回目の当記事では、長野県伊那市の仙醸(せんじょう)を特集します。 150年の歴史を誇る信州高遠の蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1866年、「天下第一の桜」で知られる信州高遠に太松酒造店として創業。その後、仙丈ケ岳にちなんで仙醸と名を変え、酒造りの伝統を受け継いできました。 2つのアルプスに囲まれ、ミネラル豊かな伏流水にも恵まれ、良質な酒米を育むのに最適な風土となっています。 高遠城跡に植え ...
「 山と、水と、ともに生きる」【白馬錦、le lac】薄井商店‐長野県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第150回目の当記事では、長野県大町市の白馬錦(はくばにしき)を特集します。 北アルプスの清冽な水と恵まれた自然で生まれたお酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業は明治39年です。二代目蔵元 薄井芳介により銘峰白馬三山にちなんで『白馬錦』と銘名されました。 北アルプスの麓、標高700m余りに位置する大町市に酒蔵をかまえ、地元大町市の契約栽培米と北アルプスの清冽な水、恵まれた自然環境のもとで酒造りを続け ...
「伝統と革新が調和した進化を続ける酒蔵」【翠露】株式会社舞姫‐長野県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第144回目の当記事では、長野県諏訪市(すわし)の株式会社舞姫(まいひめ)を特集します。 伝統と革新が共存する120年以上の歴史と、新たな出発を迎えた酒蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1894年(明治27年)に醤油、味噌の醸造元であった亀源醸造から分家し亀泉酒造として酒造りを始めました。大正天皇即位の際には、酒を献上したそうです。 2014年に、舞姫酒造株式会社を、株式会社舞姫として新たに酒造りを開 ...
日々の晩酌から特別なひと時にも“やっぱり旨い!大雪渓”が幸せづくりをお手伝いします 【大雪渓】大雪渓酒造-長野県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第131回目の当記事では、長野県北安曇郡(きたあづみぐん)の大雪渓(だいせっけい)酒造を特集します。 山々の多くの恩恵を受けながら醸しだされる「山の酒」 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業は1898年(明治31年)。北アルプスの銀嶺の下、豊富な湧き水と広大な安曇野の穀倉地帯で古くは「桔梗正宗」(ききょうまさむね)、「晴光桜」(せいこうざくら)の銘柄で親しまれてまいりました。 戦後(昭和24年)、「大雪 ...
地域と共に、伝統と文化をつなぐ【今錦、年輪、おたまじゃくし、中川村のたま子】米澤酒造-長野県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第118回目の当記事では、長野県上伊那郡(ながのけんかみいなぐん)の米澤酒造(よねざわしゅぞう)株式会社を特集します。 南アルプスの麓の自然環境と良質の水で行う丁寧な酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 明治40年、南信州のほぼ中央にある中川村で創業しました。地域に親しまれ、南アルプスの麓の自然環境と良質の水に恵まれた土地で地元の酒米を使用した酒造りを行ってきました。縁あって平成26年にかんてんぱぱグ ...
水尾山の天然水と地元酒米を使って地元嗜好の酒を造る【水尾】田中屋酒造店-長野県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第92回目の当記事では、長野県飯山市(ながのけんいいやまし)の株式会社田中屋酒造店(たなかやしゅぞうてん)を特集します。 天然水を運び仕込水として使う ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 明治6年創業。甲斐武田家の末裔、武田貢一が田中家に養子に来た時より酒造業を創業しました。より良い酒質を目指し、平成4年に野沢温泉村「水尾山(みずおさん)」の天然水を運び仕込水として使い始め、現在のブランド「水尾」が立ち上が ...
岐阜県
創業1680年、下呂温泉の恵みを受け継ぐ食中酒の蔵【天領】天領酒造‐岐阜県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第259回目の当記事では、岐阜県下呂市(げろし)の天領酒造(てんりょうしゅぞう)を特集します。 九代に渡り、脈々と受け継がれる酒蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業1680年 天下の三名泉の下呂温泉で酒造りをしています。 現在の滋賀県日野市上野田(コウズケダ)にて家を興す。蒲生氏郷公の家臣として近江地方で地盤を築き、日野屋佐兵衛と称し江戸時代(1680年)から江州日野から本州一円を巡って行商をしてい ...
創業享保5年(1720年)緑と清流の里で300年以上続く酒蔵【初緑、奥飛騨】奥飛騨酒造‐岐阜県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第252回目の当記事では、岐阜下呂市(げろし)の奥飛騨酒造(おくひだしゅぞう)を特集します。 自然に恵まれた豊かな酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業享保5年(1720年)、ここ飛騨の地で酒造りをはじめて300年以上になります。代表銘柄は、初緑と奥飛騨です。 初緑は尾張のお殿様から頂いた創業銘柄になります。ここ飛騨金山は、馬瀬川と飛騨川の合流地点になります。 この豊かな伏流水を使用し、お酒を醸し ...
造る・味わう・買うの3拍子揃った「日本酒のテーマパーク」【四ッ星】舩坂酒造店‐岐阜県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第234回目の当記事では、岐阜県高山市(たかやまし)の舩坂酒造店(ふなさかしゅぞうてん)を特集します。 飛騨高山の伝統酒蔵と味覚の楽園 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 江戸時代末期より約200年以上、飛騨高山の「古い町並」で酒造りを営む酒蔵。 観光土産品とともに直接お客様に枡酒を楽しんでいただける「直売小売店」、飛騨牛等の飛騨の味覚と共に日本酒を楽しんでいただく食事処「味の与平」を併設し「造る」「味わう ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第172回目の当記事では、岐阜県美濃市(みのし)の小坂(こさか)酒造場を特集します。 歴史と伝統が息づくうだつ造りの主屋と長良川の恵み ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 安永元年(1772年)創業の酒蔵です。創業時より使用しているうだつ造りの主屋は国の重要文化財に指定されています。 蔵の中には江戸時代を偲ばせる雰囲気がたくさん漂っています。原料水には有機ミネラルが富んだ、長良川の伏流水を井戸で汲み上げて使 ...
~「 郷土と歴史に育てられた酒造り 」~【明尽、唯々】竹内酒造‐滋賀県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第165回目の当記事では、滋賀県湖南市の竹内(たけうち)酒造を特集します。 口に出せないほどの美味しさ ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 東海道五十三次の宿場町の一つ石部の町は、必ず旅人が立ち寄った宿場町として栄ました。旅先で酒を飲み比べた旅人の間で「石部の酒」の評判が高まり人々がやって来たと言われています。 あまりに美味しいこの酒を自分のものにしておきたいとする心理から、口をつぐませ評判のその酒を訪ねて ...
「"玲瓏馥郁"を信条としたエレガントな味の酒を醸し続けます」【女城主】岩村醸造‐岐阜県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第162回目の当記事では、岐阜県恵那市の女城主(おんなじょうしゅ)を特集します。 天然水の贈り物、恵那の誇り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 江戸・天明7年(1787年)創業。岩村城下町に蔵を構え、鎌倉時代に築城された岩村城を織田信長の叔母が守ったことから「女城主」ブランドが生まれました。 現在まで恵那市内で酒造りをしている唯一の蔵元。400年前に掘られた井戸より湧き出る清らかな天然水で仕込みます。 ― ...
係数管理と官能的判断を組み合わせた品質管理【三千盛】三千盛-岐阜県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第119回目の当記事では、岐阜県多治見市(ぎふけんたじみし)の株式会社三千盛(みちさかり)を特集します。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 江戸後期の安永年間(1772〜1780)に初代水野鐵治が開業し、現在、私(水野鉄治)で6代となります。 先代である水野高吉(父)は次男であったため鐵治を襲名せず(長男である父の兄は鐵一といい、サイパンで戦死)、昭和30年6月30日私が長男として生まれた時「鉄治」と命名 ...
原料の生産から、仕込み、嗜みまで、とことん地元に拘った真の地酒造り【射美】杉原酒造-岐阜県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第117回目の当記事では、岐阜県揖斐郡(ぎふけんいびぐん)の杉原酒造(すぎはらしゅぞう)株式会社を特集します。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業は明治25年です。揖斐川と根尾川の輪中穀倉地帯において日本酒製造を営んでいます。岐阜県の酒造好適米『揖斐の誉』を自社開発し、小さい酒蔵ながら拘った清酒製造を行っています。 全国25店の特約店でのみ販売している「射美」 ―代表銘柄は? 「射美」です。弊社小売部 ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第108回目の当記事では、岐阜県高山市(ぎふけんたかやまし)の有限会社原田酒造場(はらだしゅぞうじょう)を特集します。 厳しい冬季寒仕込みによりじっくりと醸しだされた味わい ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 小京都・飛騨高山は、天正十三年(1585年)の豊臣秀吉公配下・金森長近(かなもりながちか)公の入府・高山城築城以来、金森氏六代の開発により、中世城下町として確立されました。二代高山城主・金森可重(かな ...
新生平田がチャレンジする「酒は醸し育てる」酒造り【飛鷺、多賀山、昇龍乃舞】株式会社平田酒造場-岐阜県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第98回目の当記事では、岐阜県高山市(ぎふけんたかやまし)の株式会社平田酒造場(ひらたしゅぞうじょう)を特集します。 自然豊かで整った気候条件で醸す、美味しい酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 平田家は「打保屋」の屋号で、明和6年(1769年)びんつけ油、ろうそくの製造販売を創めました。酒造業は明治28年に創業しています。創業以来研鑚をかさね、酒は醸し育てるもの、とのコンセプトのもと、手造りにこだわ ...
静岡県
遠州掛川小貫の里で150年高天神の名水で醸す美味い酒 【開運】土井酒造場‐静岡県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第238回目の当記事では、静岡県掛川市(かけがわし)の土井酒造場(どいしゅぞうじょう)を特集します。 高天神城の源泉から誕生、150年の酒蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 明治5年(1872年)、初代土井弥市は16歳で創業しました。高天神城の源泉から毎日水を蔵まで運んで酒を仕込みました。 それ以来150年間、高天神城の水を使用し、一貫して日本酒造りを続けています。 ―代表銘柄は? 「開運 祝酒 特別本 ...
創業元治元年からの酒造り、静岡の米100%にこだわる地酒【花の舞】花の舞酒造‐静岡県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第235回目の当記事では、静岡県浜松市(はままつし)の花の舞酒造(はなのまいしゅぞう)を特集します。 古来の奉納おどりから生まれる花の舞 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 花の舞の創業者、高田市三郎が遠江国あらたま村宮口で清酒製造業を始めたのは江戸末期の元治元年(1864年)です。 元治元年はペリーが浦賀に来航した11年後、桜田門外の4年後、大政奉還の3年前に当たります。 花の舞の銘柄は天竜川系に古来から ...
清冽な湧水と海の幸に恵まれた革新を続ける蔵元【英君】英君酒造‐静岡県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第205回目の当記事では、静岡県静岡市(しずおかし)の英君酒造(えいくんしゅぞう)を特集します。 駿河湾の贈り物、美食と海の幸が交わる魅力の地 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1881年(明治14年)に地元の大地主から分家して創業。徳川の英でた君主(慶喜公)にあやかって酒銘を英君とした。分家であったため酒米を各地から買い求めお酒を仕込んだ。 地元に湧出する水と駿河湾という海の幸に恵まれ、食事とお互いに引 ...
「 10種類以上の酒米で表現する、味わいの多彩さ」【臥龍梅】三和酒造‐静岡県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第151回目の当記事では、静岡県静岡市の臥龍梅(がりゅうばい)を特集します。 三和酒造の起源、夢に見た清泉から ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 三和酒造の発祥は貞享3年(1686年)に遡ります。初代市兵衛が酒造用の良水を授けたまえと祈願したところ、夢に鶯と化した稲荷大明神が現れ、満月の夜に市兵衛を導いて浅間山麓の梅の枝に止まり、その地を掘ってみると清泉を得られて、酒造業をはじめたと伝えられています。 そ ...
生酛・山廃造りによるコクと深みのある味わいを探求する酒蔵【杉錦】杉井酒造-静岡県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第101回目の当記事では、静岡県藤枝市(しずおかけんふじえだし)の杉井酒造(すぎいしゅぞう)を特集します。 戦中戦後もしっかりとした味わいの酒で地元の信用を築く ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 酒蔵のある静岡県志太平野は静岡県中部に位置しは南アルプスを源流とする大井川の扇状地で豊かで良質な水と米に恵まれ、昔から酒蔵の多い地域でした。藤枝は東海道の宿場町として発展してきており、志太平野には現在も良質な清酒 ...
表現を届ける、地域と結びついた酒造りを目指して【萩錦、駿河酔、登呂の里】萩錦酒造株式会社-静岡県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第100回目の当記事では、静岡県静岡市(しずおかけんしずおかし)の萩錦酒造(はぎにしきしゅぞう)株式会社を特集します。 地元の人に愛される丁寧に造られたお酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1876年(明治9年)から日本酒を製造する造り酒屋で、静岡県静岡市の中心街から車で20分、海の近くに位置した家族3名で守る小さな酒蔵です。初代 萩原新吉がこの土地の豊富な水に惚れ込み酒を造りはじめ、現在は5代目になり ...
愛知県
木曽川の伏流水の使用し、創業以来の伝統製法の酒造り【木曾三川(きそさんせん)】内藤醸造‐愛知県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第278回目の当記事では、愛知県稲沢市(いなざわし)の内藤醸造(ないとうじょうぞう)を特集します。 内藤醸造、文政の時代から現代へ ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1826年(文政9年)当時の尾張藩主より年貢米から酒の製造を初代、内藤利助が賜り創業致しました。近くを流れる木曽川の伏流水、県内の米等を創業以来の伝統製法、継承された技術を持って大切にま持ち続けております。 直近では3年連続で全国新酒鑑評会で ...
「伝統とは古き力を克服する新しい魂なり」美味しいのその上のときめきを【四海王】福井酒造‐愛知県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第247回目の当記事では、愛知県豊橋市(とよはしし)の福井酒造(ふくいしゅぞう)を特集します。 手造りの魂、最新技術で磨く ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 福井酒造の歴史は、明治45年に始まります。初代福井盛太郎氏が、「三河の国・田原藩」の藩主であった戸田氏からその家陣跡を拝領し、戸田家の家紋入りの井戸でお酒を仕込んだのが、その始まりとされています。 福井酒造では、創業以来一貫して手作業を基本とした丁寧 ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第242回目の当記事では、愛知県岡崎市(おかざきし)の丸石醸造(まるいしじょうぞう)を特集します。 334年の伝統が生み出す岡崎の銘酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 丸石醸造は1690年愛知県岡崎にて日本酒造りを始めました。以来334年の永きに渡り、日本酒を造り続けています。 蔵のある岡崎市は、江戸太平の世を築いた徳川家康公生誕の地という古くからの歴史があり、一方では山と川に囲まれた、豊かな自然を感じ ...
手作りで造る日本酒の伝統と、先進設備を融合させた酒造り【我山】鶴見酒造-愛知県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第134回目の当記事では、愛知県津島市(つしまし)の鶴見酒造(つるみ)を特集します。 150年の歴史があり、木曽川の伏流水に恵まれ酒蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 鶴見酒造は、尾張(愛知県西部)の地で創業から150年の歴史がある酒蔵。創業初期より「神守村の鶴見さんが造ったお酒として、神守鶴との銘柄でお酒を販売し地元のお客様を中心にご愛顧頂きました。 そこから会社の敷地内で汲みあげる木曽川の伏流水を使 ...
歴史と伝統で培われた確かな技術【清洲城信長鬼ころし、濃姫の里隠し吟醸、祥鳳、楽園延寿】清洲桜醸造-愛知県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第132回目の当記事では、愛知県清須市(きよすし)の清洲桜醸造(きよすざくらじょうぞう)を特集します。 天下統一はじまりの地「清洲城」である蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 嘉永6年(1853年)創業以来、長年の伝統と品質本位の姿勢を継続し、「清洲城信長 鬼ころし」の銘柄で消費者の支持を得てまいりました。また変化する消費者ニーズに応え、「愛知クラフトウイスキー/ジン/ウォッカ」「本格焼酎 天下泰平」「 ...
「1人で」から「2人で」に。人に寄り添いともに楽しむお酒を繋いでいく【千瓢、千瓢 奏、めぐる】水谷酒造-愛知県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第110回目の当記事では、愛知県愛西市(あいちけんあいさいし)の水谷酒造(みずたにしゅぞう)株式会社を特集します。 創業当時の江戸・大正・昭和に建てた蔵を全て現役で稼働 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 江戸時代末期に愛知県西部で治水事業を務めた水谷治ェ衛門が創業し、180年あまりの歴史があります。 創業当時の江戸・大正・昭和に建てた蔵を全て現役で稼働させており、時代の変遷を感じられる蔵構えです。 木曽、 ...
妥協なき職人魂、テロワールを大切にした酒造り【奥】山﨑-愛知県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第74回目の当記事では、愛知県西尾市 (あいちけんにしおし)の山﨑(やまざき)合資会社を特集します。 愛知県ならではの特徴が出せる酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業は明治36年。愛知県西尾市に所在し、愛知県西三河地区はみそ、しょうゆ、みりん等醸造文化が盛んな地域です。 この地域ではみそカツやどて煮など味付けがしっかりした料理が特徴で、弊社ではこの地域の食べ物の味付けに負けないような原酒でしっか ...
三重県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第285回目の当記事では、三重県四日市市(よっかいちし)の石川酒造(いしかわしゅぞう)を特集します。 石川酒造の噴井で育まれる酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1830年(天保元年)創業の「石川酒造」は敷地内に昔からの面影を残す木造の建物が並び、2012年に国の登録有形文化財として主屋をはじめ15棟の建物が登録されました。 お酒造りで使用する仕込み水は、鈴鹿山系の伏流水である超軟水の水を使用。敷地 ...
熟練杜氏が自然派の酒造りで味わい深い酒を醸す酒蔵 【鈿女(うずめ)】伊藤酒造‐三重県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第275回目の当記事では、三重県四日市市(よっかいちし)の伊藤酒造(いとうしゅぞう)を特集します。 伝統を守り、テロワールを追求する三重の名酒『鈿女』 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1847年に初代伊藤幸右衛門が創業。戦前は「伊勢櫻」の銘柄で好評を博しましたが、戦時中にやむなく廃業。戦後復活し、技術屋の4代目が早期に吟醸酒を製造し全国新酒鑑評会で金賞を受賞。「鈿女」と名付けられた美酒は三重の吟醸酒の走 ...
創業177年の歴史で育んだ「品質本位」の精神【宮の雪】宮崎本店‐三重県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第256回目の当記事では、三重県四日市(よっかいちし)の宮﨑本店(みやざきほんてん)を特集します。 高品質を追求し、新たな価値を生み出す蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 宮﨑本店は1846年の創業以来、四日市市楠町で「品質本位」を第一に確かな製品を作り続けてきました。 どの製品に関しても高い品質を維持しながら現状に満足することなく日々探求を続け、時代にあった製品をご提供していきます。 ―代表銘柄は? ...
「美味しい日本酒を鈴鹿から世界へ」【作】清水清三郎商店‐三重県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第154回目の当記事では、三重県鈴鹿市の作(ざく)を特集します。 三重県鈴鹿の酒蔵が織りなす、神々の食卓への調和 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1869年創業。三重県鈴鹿市の伊勢湾に面した酒蔵です。三重の酒は伊勢神宮との関係が深く、弊社も例外ではありません。 酒米はお伊勢参りに来た人々が日本中に広めたという説がありますし、1500年以上前から、日毎朝夕大御食祭という食べ物をつかさどる豊受の神(外宮)で ...
神の水、伊勢の風、式 SHIKI 【式 SHIKI】河武醸造株式会社‐三重県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第141回目の当記事では、三重県多気郡(たきぐん)の式SHIKI(しき)を特集します。 8代にわたる醸造の歴史と、新たな挑戦。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 安政4年(1857年)に創業、現社長で8代を数えます。味噌・醤油の醸造事業から操業を開始しましたが、途中で清酒醸造事業を開始し、現在では清酒醸造がメインとなっています。 地元では長年「鉾杉(ほこすぎ)」という銘柄でご愛顧いただいてきましたが、20 ...
夫婦で酒を醸す小さな酒蔵。米の旨味を愉しめる酒造り【青雲、颯】合資会社後藤酒造場-三重県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第41回目の当記事では、三重県桑名市(みえけんくわなし)の後藤酒造場(ごとうしゅぞうじょう)を特集します。 桑名の台所に豊かな水を供給する町屋川のほとり ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業大正6年(1917年)です。 東海道の宿場町、「七里の渡」で有名な伊勢国の玄関口「桑名」は、木曾三川(きそさんせん)の河口に位置し、その豊かな水運と尾張・美濃・伊勢という穀倉地帯(こくそうちたい)を背景に、古来より日 ...
地元の酒米や酵母の特徴を活かした酒造り【半蔵】株式会社大田酒造-三重県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第15回目の当記事では、三重県伊賀市(みえけんいがし)の大田酒造(おおたしゅぞう)を特集します。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 明治25年創業。大田酒造は四方を山々に囲まれた伊賀盆地のほぼ中央に位置します。周囲は白鷺が飛び交う豊かな田圃に囲まれた地で、手作業にこだわった少量の造りを行っています。 また、伊賀は400万年前、古琵琶湖の底でした。その為、粘土質な土壌が上質なお米を育てる環境にあります。伊賀 ...
「口中で広がって喉で消える」酒質を目指す【三重の寒梅、伊勢正宗、はま娘】丸彦酒造株式会社-三重県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と日本酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第5回目の当記事では、三重県四日市(みえけんよっかいちし)の丸彦酒造(まるひこしゅぞう)を特集します。 酒造りの原点に立ち返り「本物の日本酒・真の日本酒」の考えから生まれた「三重の寒梅」 ―酒蔵の歴史について教えて下さい。 藤原大地 社長 丸彦酒造株式会社は今から約150年前の慶応3年(1867年)に鈴木彦左衛門が創業した現在で7代続く酒蔵です。彦左衛門はこの地の地主で、小作から地代として受け取る年貢米が豊富に ...
滋賀県
甲賀流忍者発祥の地、滋賀県甲賀市に位置する酒蔵【忍者】瀬古酒造‐滋賀県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第248回目の当記事では、滋賀県甲賀市(こうがし)の瀬古酒造(せこしゅぞう)を特集します。 忍者の里で育まれた酒蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 甲賀忍者の里は滋賀県甲賀市甲賀町にあり、明治2年に創業されました。創業以来、地元の米と鈴鹿山系伏流水の井戸水を使用して酒造りを行っています。代表銘柄である「忍者」は登録商標です。 ―代表銘柄は? 「忍者 純米大吟醸 ラムール」 播州産「愛山」100%の忍者で ...
「地の恵み」を大切に、滋賀県産米の性格を素直に表現した酒造り【大自然しんかい】藤本酒造-滋賀県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第46回目の当記事では、滋賀県甲賀市(しがけんこうかし)の藤本酒造(ふじもとしゅぞう)株式会社を特集します。 神様のお告げにより出来た清酒「神開(しんかい)」 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 当酒蔵は滋賀県と三重県との県境に位置し、甲賀忍者(こうかにんじゃ)の里として知られる甲賀市(こうかし)にあります。その昔、明和元年(1763)ごろより、先祖が「宝一」の名で清酒を造っておりましたが、あまり酒質が良く ...
美しく冨くよかで恒久に続く酒造り【美冨久、三連星】美冨久酒造株式会社-滋賀県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第24回目の当記事では、滋賀県甲賀市(しがけんこうかし)の美冨久酒造(みふくしゅぞう)を特集します。 「水口」の名前は水が綺麗で豊富な事からつきました。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1917年(大正6年)甲賀忍者の郷であり東海道五十三次50番目の宿場町「水口宿」の入り口に蔵を構えております。この「水口(みなくち)」とはその名前通り水が綺麗で豊富な事から名づけられており、現在でもこの町の中だけで5軒の ...
食べながら呑んでいたら、いつの間にか無くなっている酒造り【浅茅生】有限会社平井商店-滋賀県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第12回目の当記事では、滋賀県大津市(しがけんおおつし)の平井商店(ひらいしょうてん)を特集します。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 万治元年(1658年)創業。京都へ至る東海道五十三次最後の宿場「大津宿」、その旧東海道の一本北の通りに弊社はあります。京都で消費されるのに「大津酒」という言葉があるほど旧大津市街地では酒造が盛んで、元禄10年(1697年)頃には77軒もの酒屋が軒を連ねていたといいます。現 ...
自然の恵みをそのままいただく酒造り【春乃峰】田中酒造株式会社-滋賀県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第9回目の当記事では、滋賀県甲賀市(しがけんこうかし)の田中酒造(たなかしゅぞう)を特集します。 甲賀地域は近江米の米どころであり、鈴鹿山系の豊富な伏流水が流れる ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 ここ甲賀地域は近江米の米どころ、鈴鹿山系の豊富な伏流水、また東海道の宿場町、街道沿いということもあり古くからたくさんの酒屋、酒蔵がありました。現在も滋賀県33蔵のうち11蔵が旧甲賀郡地域で営んでおります。 田中 ...
京都府
米、水、麹、心意気。ただ良い酒を、350年。 【玉乃光】玉乃光酒造‐京都府
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第264回目の当記事では、京都府京都市(きょうとし)の玉乃光酒造(たまのひかりしゅぞう)を特集します。 京都伏見の伝統を守り続ける純米吟醸蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1673年、紀州徳川藩の御用蔵として創業。八代将軍吉宗公もご愛飲された350年の歴史ある京都伏見の蔵元です。 1964年『無添加酒』(今の純米酒)を発売。以来『手造り品質第一主義』に徹し、農家との契約栽培化、自社扁平精米、麹は全量手 ...
昔ながらの生酛仕込みにこだわる丹波地酒【翁鶴】大石酒造‐京都府
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第211回目の当記事では、京都府亀岡市(かめおかし)の大石酒造(おおいししゅぞう)を特集します。 美山町の自然で育まれた酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 元禄年間創業 300年の歴史のある酒蔵です。10年ほど前には、かやぶきで有名な美山町に仕込み蔵を新設し、芦生の源流水を使用し自然豊かな場所で仕込みをしております。 ―代表銘柄は? 「翁鶴 上撰」 やや甘口で、冷酒から燗酒までお好きな温度でお楽しみいた ...
久美浜からの贈り物、丹誠の地酒 【久美の浦】熊野酒造‐京都府
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第203回目の当記事では、京都府京丹後市(きょうたんごし)の熊野酒造(くまのしゅぞう)を特集します。 湾に映える久美の酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1921年、亀屋酒店として清酒製造を開始。1944年、有限会社として改組し今に至る。 山陰国立公園の久美浜湾の岸辺にあり、酒蔵から湾が一望できる事から酒銘を「久美の浦」と命名しています。 ―代表銘柄は? 「久美の浦 純米吟醸」 純米吟醸は地元京都府産の ...
淡麗優雅を目指し、水の性質に逆らわないお酒造り【英勲】齊藤酒造-京都府
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第52回目の当記事では、京都府京都市 (きょうとふきょうとし)の齊藤酒造(さいとうしゅぞう)株式会社を特集します。 明治時代に呉服商から酒造業へ転業 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 江戸時代初期、初代・井筒屋伊兵衛が伏見で到来の旅人を主な相手に呉服商(ごふくしょう)を開業しました。 伏見はかつて京都、大阪を川船で結び、人流や物流の巨大ターミナルとして豊臣秀吉が開発しました。京都とは別の大きな町として明治 ...
丹後の美味しい食用米を全量使用した日本酒造りに励む【白木久】白杉酒造-京都府
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第48回目の当記事では、京都府京丹後市(きょうとふきょうたんごし)の白杉酒造(しらすぎしゅぞう)株式会社を特集します。 4人で約250年の歴史を守り、日本で唯一全量食用米のみで日本酒を造る ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 白杉酒造は、全量食用米のみで日本酒を造る、日本で唯一の酒蔵です。 白杉酒造のある京都府京丹後市は、京都の日本海側に面した丹後(たんご)と呼ばれる地域に位置しています。 丹後は昔から小さ ...
熟成酒へ変化していく神秘的なプロセスを大切に、五感と時間軸で深い感動を醸し出す【玉川】木下酒造有限会社-京都府
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第22回目の当記事では、京都府京丹後市(きょうとふきょうたんごし)の木下酒造(きのしたしゅぞう)を特集します。 杜氏はイギリス出身のフィリップ・ハーパー。酒造りの主テーマは『熟成』。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 京丹後市久美浜で天保13年(1842)の創業以来、約180年にわたり『玉川』の酒造りを継承しております。現在はイギリス出身のフィリップ・ハーパーが杜氏を務めており、豊かな発想力と挑戦的な酒造 ...
伝統的な木造土壁の蔵で行う力強い酒造り【初日の出、羽田、脱兎、六友】羽田酒造有限会社-京都府
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第14回目の当記事では、京都府京都市(きょうとふきょうとし)の羽田酒造(はねだしゅぞう)を特集します。 地域に合わせた、力強い酒質 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 羽田酒造は京都市京北で日本酒を製造する創業約130年の酒蔵です。当社は、京都盆地より遥か北、自然に囲まれた山間の町で酒造りをしております。桂川水系の上流部にあり標高が高いため、特に冬の気温は低く、雪景色もきれいな場所です。 ここ京北は、古都へ ...
米と水と人との調和、温故創新の酒造り【山廃本醸造酒呑童子、香田、hakurei】ハクレイ酒造株式会社-京都府
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と日本酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第4回目の当記事では、京都府宮津市(きょうとふみやづし)のハクレイ酒造(ハクレイしゅぞう)を特集します。 由良ヶ岳から流れる仕込み水。硬度11.2mg/Lの超軟水は酒の味を甘口でも辛口でも自在に醸す。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 京都府宮津市の丹後由良で1832年に創業し、江戸時代から続く伝統の酒蔵です。多くの受賞歴ある日本酒やリキュールを製造しております。常に地域に根差し、愛され、奉仕・貢献でき ...
チャレンジを続ける美感遊創の酒造り【城陽、徳次郎】城陽酒造株式会社-京都府
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と日本酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第3回目の当記事では、京都府城陽市(きょうとふじょうようし)の城陽酒造(じょうようしゅぞう)を特集します。 温暖な気候と木津川の伏流水に恵まれた自然豊かな土地 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 城陽酒造は京都から五里、奈良から五里という場所に位置しており、温暖な気候と木津川の伏流水に恵まれた自然豊かな地で1895年「島本酒造部」を組織し現在の酒蔵を新造して創業しました。その後1973年には「城陽酒造株式 ...
大阪府
酒に酔い、人に酔い、夢に酔う【大門、利休梅】大門酒造‐大阪府
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第282回目の当記事では、大阪府交野市(こうのし)の大門酒造(だいもんしゅぞう)を特集します。 二百年の歴史と清水ヶ谷の恵み ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 大門酒造は文政九年(1826年)、生駒山系の山並みの麓、交野ケ原の無垢根村に創業いたしました。 以来約二百年、いくつもの時代を超えて一心に酒造りに励んでおります。 大阪、京都、奈良と三つの都に囲まれた交野は古くは恰好の米の産地として知られ、また背後 ...
安心安全で佳い酒を少しずつをモットーに造る酒造り【荘の郷、都娘、しょうのさと】有限会社北庄司酒造店-大阪府
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第32回目の当記事では、大阪府泉佐野市(おおさかふいずみさのし)の北庄司酒造店(きたしょうじしゅぞうてん)を特集します。 全社員が、全工程を、昔ながらの手作業にて造る。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 日本遺産認定「日根荘」の風景が息衝く恵まれた地にて大正10年創業、関西国際空港の対岸、泉佐野市唯一の醸造蔵です。1921年と1925年建立の大型木造蔵2棟を有し、約70年前から当時“幻の酒”と呼ばれた吟醸 ...
兵庫県
生粋の灘酒、全国唯一の伊勢神宮御料酒蔵元【白鷹】白鷹‐兵庫県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第255回目の当記事では、兵庫県西宮市(にしのみやし)の白鷹(はくたか)を特集します。 西宮の老舗:超一流主義・品質第一主義 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1862年(文久2年)辰馬悦蔵が『超一流主義・品質第一主義』を掲げ西宮の地に白鷹を創業。 『水』・『米』・『造り』にとことんこだわり抜き、堅実に酒を造ってきました。 創業者から脈々と続く意志を体現し、伝統を重んじながらも、「変えないもの」「変えるも ...
酒造りを見て、感じて、味わえる!大人も子供も楽しめる「発酵文化の体感空間」【浜福鶴】小山本家酒造 灘浜福鶴蔵‐兵庫県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第251回目の当記事では、兵庫県神戸市(こうべし)の灘浜福鶴蔵(なだはまふくつるぐら)を特集します。 震災を乗り越えた強い絆 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 「浜福鶴」は明治初期(1900年頃)からこの地で酒造りを営み、当時は「大世界」という銘柄でその名を馳せました。 その後、昭和の大戦時に国の企業整備があり、終戦後の1950年に「福鶴」を名乗り酒造業を再開、1989年に「世界鷹小山家グループ」へ加入し ...
伝統を受け継ぎながら、“発酵”で挑戦し続ける酒蔵【小鼓】西山酒造場‐兵庫県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第245回目の当記事では、兵庫県丹波市(たんばし)の西山酒造場(にしやましゅぞうじょう)を特集します。 世界35ヶ国以上への誇りある酒蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1849年(嘉永2年)創業。アルコールに限らず、170年以上続く酒造りのノウハウ、「米の発酵技術」を活かして、子供からお年寄りまで楽しんでいただける新しいモノづくりに、挑戦しています。 また、今では世界35ヶ国以上への輸出や、世界的な品 ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第227回目の当記事では、兵庫県丹波篠山市(たんばささやまし)の狩場一酒造(かりばいちしゅぞう)を特集します。 地元からの愛飲、大正から続く酒蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 弊社は、大正5年(1916年)に丹波杜氏の狩場藤蔵(とうぞう)が創業した酒蔵になります。初代社長にあたる狩場藤蔵は、灘のみならず九州でも酒造りの指導を行うなど、腕の立つ杜氏であったと聞いております。 杜氏が建てた蔵という事もあ ...
すべての人に酒と笑いと幸せを、モットーに日本酒を世界へ【明石鯛】明石酒類醸造‐兵庫県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第209回目の当記事では、兵庫県明石市(あかしし)の明石酒類醸造(あかししゅるいじょうぞう)を特集します。 古都明石の酒、世界への誇り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 酒蔵のある兵庫県明石市は、平安時代源氏物語にも歌われた風光明媚な瀬戸内海に面した港町です。1860年江戸末期より醸造業(醤油製造)や両替商を営み、1960年から日本酒の製造を始めました。現在は、年間を通して地元兵庫県産の酒米だけを使い日本 ...
田舎の極小蔵とファンが一体となる新しい日本酒の楽しみ方【雪彦山】壺坂酒造‐兵庫県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第206回目の当記事では、兵庫県姫路市(ひめじし)の壺坂酒造(つぼさかしゅぞう)を特集します。 辨慶酒米の蘇り、400年から続く醸造 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 壺坂酒造は1629年より姫路市香寺町にて酒造りを始め、1805年現在の地姫路市夢前町に移転しました。当時の弊社6代目当主「善造」が建設した酒蔵は、現在も弊社の発酵環境の源となる宝であり、2008年に姫路市の都市景観重要建築物に指定されました ...
1702年創業、食中熟成純米燗酒を醸す全量地元米純米蔵【竹泉】田治米合名会社‐兵庫県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第168回目の当記事では、兵庫県朝来市の竹泉(ちくせん)を特集します。 伏流水と地元米でつくる至高の味わい ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業元禄15年、現当主で19代目になります。 仕込み水に“竹の川”の伏流水を使用し、先祖の出身地である和泉の国の田治米村(現在の大阪府岸和田市田治米町)から取り酒銘“竹泉”となづけております。 自然に感謝し、先祖を尊ぶ気持ちを表しております。 2012年より全量純米 ...
「 日本酒とウイスキーの二刀流、創立135年になる酒類総合メーカー 」【神鷹・日本魂】江井ヶ嶋酒造‐兵庫県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第166回目の当記事では、兵庫県明石市の江井ヶ嶋(えいがしま)酒造を特集します。 多様な醸造を行う蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 初代社長のト部兵吉は、明治21年(1888年)に江井島地区の酒造業者に呼びかけ、 江井ヶ嶋酒造株式会社を設立しました。 大正時代からウイスキー、みりん、焼酎も造り始め、後に山梨にワイナリーを開設。 ―代表銘柄は? 「神鷹(かみ(たか) 純米酒水もと仕込み 」 水もと(菩提 ...
清酒を造り続けて400年、協会一号酵母発祥蔵【櫻正宗】櫻正宗株式会社‐兵庫県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第139回目の当記事では、兵庫県神戸市(こうべし)の櫻正宗(さくらまさむね)を特集します。 初めて公的酵母として配布された「協会一号酵母」の発祥蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1625年創醸の櫻正宗は、多くの酒銘に使用されている「正宗」の元祖蔵です。6代目当主山邑太左衛門が「臨済正宗(りんざいせいしゅう)」という経典を見て、正宗と清酒の語音が似ていることから、1840年に酒銘に初めて「正宗」と名付け ...
自然の恵み豊かな風土とお客様に支えられ、創業360周年【白鹿】辰馬本家酒造-兵庫県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第136回目の当記事では、兵庫県西宮市(にしのみやし)の辰馬本家酒造(たつうまほんけ)を特集します。 「品質第一」を追求している酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 兵庫県西宮の地で、宮水、良質の米、六甲おろしといった自然の恵み豊かな風土に支えられ、1662年(寛文2年)の創業以来360年にわたって酒を造り続けてまいりました。 戦争や震災により多くの蔵を失いましたが、1993年に完成した「六光蔵」では ...
奈良県
「吉野杉の樽酒」を創業以来、提案し続ける酒蔵 【吉野杉の樽酒】長龍酒造‐奈良県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第265回目の当記事では、奈良県北葛城郡(きたかつらぎぐん)の長龍酒造(ちょうりょうしゅぞう)を特集します。 長龍酒造の酒米とクラフトビールへの挑戦 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1963年に長龍酒造は設立しました。 いい酒を醸すには、安心安全な、いい酒米が不可欠。そんな想いから地元奈良の酒造好適米「露葉風」を山添村農家様と、そして「雄町米」発祥の地である岡山県高島地区とも委託栽培を開始し、米と寄り添 ...
蔵に寄り添う酒造り、目指すは究極の食中酒【黒松稲天】稲田酒造‐奈良県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第240回目の当記事では、奈良県天理市(てんりし)の稲田酒造(いなたしゅぞう)を特集します。 天理の歴史と自然に育まれた清酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 日本最古の道、山の辺の道、数々の歴史・文化遺産を有する天理。自然豊かなその地にて明治10年創業より土地の水、土地の米、土地の人にこだわる清酒「黒松稲天」を醸す清酒製造業を営み、又、上質な酒粕、新鮮野菜で漬け込む奈良漬も昭和45年より製造販売しており ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第195回目の当記事では、奈良県奈良市(ならし)の今西清兵衛商店(いまにしせいべえしょうてん)を特集します。 春鹿の伝説から継ぐ、伝統の息吹蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 今西家は明治17年(1884年)より酒造業を始めました。酒銘の由来は、春日の神々が鹿に乗って奈良の地へやってきたという伝説から「春日神鹿」(かすがしんろく)と名付け後に「春鹿」(はるしか)に改め今日に至っております。 ―代表銘柄は ...
国定公園の清らかな地下水と雄町米で醸すふくよかな酒【百樂門】葛城酒造株式会社‐奈良県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第148回目の当記事では、奈良県御所市(ごせし)の葛城酒造 (かつらぎ)を特集します。 奈良の伝統を受け継ぎ、手作業にこだわった『百樂門』 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 奈良県大宇陀町(現宇陀市)にある本家(現久保本家酒造・元禄年間創業)より明治20年に現在の奈良県御所市に分家、江戸時代の油屋に酒蔵を構えました。奈良盆地の西の金剛・葛城国定公園の麓に位置しています。 手作業にこだわった小仕込みを行って ...
井戸から汲み上げた地下水で飲み飽きない酒造りがモットー【篠峯、櫛羅】千代酒造-奈良県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第49回目の当記事では、奈良県御所市(ならけんごせし)の千代酒造(ちよしゅぞう)株式会社を特集します。 自社の井戸で汲み上げた葛城山の地下水を仕込み水に使用した日本酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 「櫛羅(くじら)」の地で創り続ける日本酒は、葛城山(かつらぎさん)の恵みである地下水を自社の井戸で汲み上げ、仕込み水にしています。 この、当たり前が続けられていることに感謝しながら、この地での酒造りに取り組 ...
再現性のある数値管理による精密な酒造り【萬穣、豊臣秀長、奈良吟】中谷酒造株式会社-奈良県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第20回目の当記事では、奈良県大和郡山市(ならけんやまとこおりやまし)の中谷酒造(なかたにしゅぞう)を特集します。 江戸時代に建てられた米蔵、酒蔵、大正の酒蔵、城館を囲んだ堀と石垣 。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 嘉永六年(1853)に創業しました。所在する番条町は15世紀に清酒発祥の地・正暦寺の酒を積み出す為に興福寺により整備された河川港の環濠集落です。 中谷酒造は創業以来河川で交通を行い、その後 ...
創業天保元年(1830年)、自社醸造再開2年目の“老舗ベンチャー酒蔵”【歓喜光、悠久の光】澤田酒造株式会社-奈良県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第19回目の当記事では、奈良県香芝市(ならけんかしばし)の澤田酒造(さわだしゅぞう)を特集します。 2019醸造年度、約30年ぶりに澤田酒造の酒造りが復活 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 奈良県には、酒造りの神様として全国の酒蔵から広く信仰を集める大神神社や、室町時代に僧坊酒の一大生産拠点として近代醸造法の基礎となる酒造技術を確立し、奈良が清酒発祥の地と言われる所以となった正暦寺があり、日本酒文化との深 ...
昔ながらの“生きた町”で醸す丁寧な酒造り【出世男、うねび、香具山、宗久】河合酒造株式会社-奈良県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第18回目の当記事では、奈良県橿原市(ならけんかしはらし)の河合酒造(かわいしゅぞう)を特集します。 今井町唯一の酒蔵、母屋は重要文化財 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 奈良盆地の中ほどにあり、大和三山に囲まれた今井町は、戦国末期に浄土真宗の寺内町として成立しました。今井町は「大和の金は今井に七分」といわれるほど栄えた商業都市であり、現在も江戸時代の街並みを有し、伝統的建造物保存地区にも指定されています ...
造り手の思いが飲む人の心に伝わる酒造り【御代菊、白檮、利兵衞】喜多酒造株式会社-奈良県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第17回目の当記事では、奈良県橿原市(ならけんかしはらし)の喜多酒造(きたしゅぞう)を特集します。 ―酒蔵の歴史について教えて下さい。 1718年(享保3年) 創業初代利兵衞(りへい)が大和三山に囲まれた大和國高市郡御坊村(現在の奈良県橿原市御坊町)で創業。1940年(昭和15年)酒蔵の移築現社屋から東に80メートル、近鉄橿原線開線当時、計画線路上にもとの酒蔵があったが、橿原神宮の皇紀2600年祭に際し行われた周 ...
和歌山県
伝統的な技術を継承し、「食を豊かにする酒」を目指す。【車坂】吉村秀雄商店‐和歌山県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第272回目の当記事では、和歌山県岩出市(いわでし)の吉村秀雄商店(よしむらひでおしょうてん)を特集します。 吉村秀雄商店の酒造りの歩み ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 大台ケ原に源流を発し、流域の自然を育みつつ紀伊水道に注ぐ紀の川。 弊蔵はその流域・岩出の地で吉村秀雄が大正4年に創業。灘で習得した酒造技術を生かした「根来桜」や「日本城」といった銘柄で長く親しまれ、2000年代に入ってから「車坂」を立ち ...
本州最南端の蔵元で、昔ながらの伝統の酒造りを守り続ける【太平洋】尾﨑酒造-和歌山県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第50回目の当記事では、 和歌山県新宮市(わかやまけんしんぐうし)の尾﨑酒造(おざきしゅぞう)株式会社を特集します。 本州最南端の蔵元 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業は明治初期。世界遺産・熊野三山(くまのさんざん)の中心に位置する本州最南端の蔵元で、和歌山県有田川町より三重県伊勢松阪周辺(約250km)の間で、ただ一軒だけの地酒メーカーです。 酒蔵のすぐ北側が、川の参詣道・世界遺産 熊野 ...
「おすし」と共に楽しめる日本酒【雑賀、雜賀孫市】株式会社九重雜賀-和歌山県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第43回目の当記事では、和歌山県紀の川市(わかやまけんきのかわし)の九重雜賀(ここのえさいか)を特集します。 「おすしの発祥の地」という地理的背景と、「赤酢」と「日本酒」を共に醸してきた歴史的背景 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 一世帯当たりの食酢の使用量が日本でもトップクラス、「おすしの発祥の地」といわれている和歌山県で赤酢の製造元として1908年に創業しました。 創業者は「より良い赤酢を製造するのに ...
鳥取県
鳥取から世界にはばたく 進化する老舗 【千代むすび】千代むすび酒造‐鳥取県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第281回目の当記事では、鳥取県境港市(さかいみなとし)の千代むすび酒造(ちよむすびしゅぞう)を特集します。 発酵文化を守り続ける日本酒造りの老舗 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1865年(慶応元年)創業。日本酒造りを基本としながら、焼酎、スピリッツ、ウイスキー等の蒸留酒、リキュールの混成酒、ノンアルコール甘酒を製造し、「発酵」という事業領域のもと、事業展開しております。 「岡空家」のファミリービジネ ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第196回目の当記事では、鳥取県米子市(よなごし)の稲田本店(いなたほんてん)を特集します。 稲田姫の手造り酒、縁と美味を共に。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 稲田本店は1673年の創業以来、山陰米子の地で手造りの心を大切にしてお酒を醸し続けております。 銘柄「稲田姫」は、縁結びの神様「稲田姫」に由来するものです。常に新しい事にチャレンジしながらも、手造りの良さと人と人とのご縁を大切に、暖簾を守ってお ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第73回目の当記事では、鳥取県東伯郡(とっとりけんとうはくぐん)の大谷酒造(おおたにしゅぞう)株式会社を特集します。 山や海の幸が豊富で畜産や農業も盛んな町 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 当社は創業明治5年で南は大山・北は日本海が一望できる鳥取県中部の琴浦町にあります。 この町から見える大山の姿は伯耆富士(ほうきふじ)とも呼ばれています。山や海の幸が豊富で畜産や農業も盛んな町です。 山菜・白いか・もさ ...
島根県
バランスよくどんな料理にも合う「食中酒」を追求し、進化を続ける創業300年以上の酒蔵 【七冠馬】簸上清酒‐島根県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第250回目の当記事では、島根県奥出雲町(おくいずもちょう)の簸上清酒(ひかみせいしゅ)を特集します。 泡無酵母の原種を発見した蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 当蔵は1700年代前半(正徳年間)に島根県・奥出雲で創業しました。長い歴史の中で数度火災に見舞われ正確な記録が消失しましたが、同じ郡内には当蔵含め5軒の酒蔵があったといわれ、古くから酒造りが盛んな地域であったことが伺えます。 1910年に町内 ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第89回目の当記事では、島根県出雲市(しまねけんいずもし)の富士酒造(ふじしゅぞう)合資会社を特集します。 日本トップレベルの清らかなお米が作られる出雲市に構える酒蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 日本酒「出雲富士」を醸造している富士酒造合資会社は、多く太古の秘密が眠る地、島根県出雲市に蔵を構えています。島根県は海、山、川、湖などの大自然に恵まれた豊かな地域で、そんな風土で栽培されるお米や野菜の清らか ...
山間の町で醸される滋味豊かなお燗酒【玉櫻、殿、とろとろにごり】玉櫻酒造-島根県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第66回目の当記事では、島根県邑智郡(しまねけんおおちぐん)の玉櫻酒造(たまざくらしゅぞう)有限会社を特集します。 兄弟二人で力を合わせた酒造りを行う玉櫻酒造 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。明治25年創業。蔵のある邑南町は、島根県の中部に位置する中国山地の山懐にいだかれた人口1万人の町です。平成16年(2004年)に長男が、平成20年(2008年)には次男が蔵へ戻り、兄弟力を合わせて酒造りをしています。 ...
人と人との心をつなぐ酒を目指して【環日本海、渦】日本海酒造-島根県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第59回目の当記事では、島根県浜田市(しまねけんはまだし)の日本海酒造(にほんかいしゅぞう)株式会社を特集します。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 島根県の西部、石見(いわみ)地方の浜田市三隅町にあり、社名の如く日本海沿岸に蔵が建っています。また三隅町は「水澄みの里」とも言われる、海・川・山が織りなす風光明媚な土地です。 1888年に創業し、食中酒を中心に、様々なタイプの日本酒を醸しています。日本国内だ ...
岡山県
創業慶応3年(1867年)星巡る町、自然と共にお酒を醸す「ドメーヌ蔵」【竹林】丸本酒造‐岡山県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第254回目の当記事では、岡山県浅口市(あさくちし)の丸本酒造(まるもとしゅぞう)を特集します。 自然と向き合うお酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業は慶応3年(1867年)、蔵の背後には東アジア最大の反射望遠鏡(口径3.8m)を装備した「竹林寺山天文台」があり、「竹林」の名前はこの山の名前より頂きました。 日本でもっとも星が綺麗に見える天文のまち岡山県浅口の地で、自然と向き合いお米から作る酒造 ...
雄町の未来は御前酒が醸す【御前酒】御前酒 蔵元 辻本店‐岡山県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第222回目の当記事では、岡山県真庭市(まにわし)の御前酒 蔵元 辻本店(つじほんてん)を特集します。 最古の酒造り、「菩提酛」を復元した蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 文化元年(1804年)創業。美作勝山藩御用達の献上酒として「御前酒」の銘を受けたことが銘柄の由来。現在は七代目蔵元辻総一郎と実姉の麻衣子が杜氏を務め姉弟で蔵を切り盛り。 令和4酒造年度より全量県産雄町での酒造りとなり、全国に先駆けて ...
白桃のようなみずみずしい酒を造りたい【桃の里】赤磐酒造‐岡山県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第207回目の当記事では、岡山県赤磐市(あかいわし)の赤磐酒造(あかいわしゅぞう)を特集します。 昭和天皇の栄誉を胸に、桃の里が奉醸する百年の歴史と誇り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 大正12年創業。備前米の主産地に位置し、朝日米等、優良米を使用し、芳醇な酒を造っています。篤農家の人々が夏は米作り、冬は酒造りに加わっています。また経営者自らも酒造りに加わり、蔵人全員精進を重ね、一期一会の良質の酒造りに ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第184回目の当記事では、岡山県倉敷市(くらしきし)の森田酒造(もりたしゅぞう)を特集します。 歴史が息づく明治の蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 明治42年創業。酒蔵と付帯施設は国の伝統的建造物に指定され、槽は稼働産業遺産としても認められています。 ―代表銘柄は? 「萬年雪 純米荒走り」 岡山県産朝日一等米を使用。純米未搾り原酒です。 お薦めの飲み方:冷酒にて ―イチオシ商品はなんですか? 「美し ...
雄町の未来は御前酒が醸す【美作、1859、菩提酛にごり酒 】辻本店-岡山県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第82回目の当記事では、岡山県真庭市 (おかやまけんまにわし)の株式会社辻本店(つじほんてん)を特集します。 雄町の未来は御前酒が醸す ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 文化元年(1804年)現在地の岡山県真庭市にて創業しました。 美作勝山藩(みまさかかつやまはん)御用達の献上酒として「御前酒」の銘を受けました。現蔵元の七代目辻総一郎の実姉である辻麻衣子が平成19年より杜氏を担っています。 「雄町の未来は ...
米作りから酒造りまで一貫した真の地酒造り【酒一筋、赤磐雄町®】利守酒造-岡山県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第81回目の当記事では、岡山県赤磐市(おかやまけんあかいわし)の利守酒造(としもりしゅぞう)株式会社を特集します。 地の米・地の水・地の気候と風土で醸す、酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 利守酒造は、岡山県の南東部、赤磐市西軽部(にしかるべ)にあります。この地は、昔から最も質の高い「雄町米」が育つ場所として知られていました。 農業の近代化とともにいつしか幻となっていた「雄町」の復活に立ち上がったの ...
広島県
日本酒の入り口となるフルーティーな広島酒【本洲一】梅田酒造場‐広島県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第213回目の当記事では、広島県広島市(ひろしまし)の梅田酒造場(うめだしゅぞうじょう)を特集します。 小さな蔵、国際受賞の誇り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 広島県広島市の東部、船越の町で「本洲一」という銘柄の地酒を造る小さな蔵元です。華やかな香りと、スッキリとした飲み口ながらしっかりとした味わいで、普段日本酒を飲み慣れない方にも分かりやすく楽しんでいただける酒が特徴です。 IWC(Internat ...
1856年創業 最高の旨さを求め続ける 広島・呉の地酒【千福】三宅本店‐広島県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第185回目の当記事では、広島県呉市(くれし)の三宅本店(みやけほんてん)を特集します。 縁起を紡ぐ酒、最高の味わいを求め ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 千福の酒銘は、初代三宅清兵衛が母『フク』と妻『千登(チト)』の名から一文字ずつとり名付けられました。社業を支え、従業員を心底慈しんだ母や妻の功労に心から感謝の想いが込められています。 縁起の良い酒銘と確かな味わいで地元に根付き、1920年には海軍から ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第145回目の当記事では、広島県三次市(みよしし)の美和櫻酒造(みわさくら)を特集します。 伝統の味わい、情熱の酒造り。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 大正12年創業、1970年に美和櫻酒造有限会社に改めました。 酒蔵のある三次市三和町は、澄んだ空気と清らかな水に恵まれた酒造好適米「八反錦」「八反」「千本錦」のふるさとです。 蔵元自らも、米作りから手掛けることにより「より良い品質の酒米、より上質の酒造 ...
こころに残るおいしいを求めて【桜吹雪、賀茂金秀】金光酒造-広島県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第72回目の当記事では、広島県東広島市(ひろしまけんひがしひろしまし)の金光酒造(かねみつしゅぞう)合資会社を特集します。 酒どころ広島をけん引してきた醸造技術 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 蔵のある場所は県南にありながら標高170mあり、冬は寒冷な気候に恵まれた環境です。 また県内では酒造好適米である千本錦、山田錦、雄町、こいおまち、八反錦、八反35を栽培しており積極的に新品種の開発を行っています。 ...
地域風土の特性を活かした、唯一無二の酒造り【龍勢】藤井酒造-広島県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第58回目の当記事では、広島県竹原市(ひろしまけんたけはらし)の藤井酒造(ふじいしゅぞう)株式会社を特集します。 「酒は、人が造るものではなく、自然が醸すもの」 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 瀬戸内海沿岸にある、江戸時代の町並みが今も残る風光明媚な町・竹原で創業し、150年を超えております。 「酒は、人が造るものではなく、自然が醸すもの」をコンセプトに、地域の風土を映し出すお酒を目指しています。 造る ...
山口県
Think Globally Act Locally 【貴】永山本家酒造場‐山口県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第186回目の当記事では、山口県宇部市(うべし)の永山本家酒造場(ながやまほんけしゅぞうじょう)を特集します。 厚東川の恵みで紡ぐミネラル豊かなお酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1888年創業。秋吉台を水源とする厚東川の伏流水(中硬水)を使用したしっかりとミネラルの感じられる辛口のお酒を造り続けています。 2015年の醸造より醸造アルコールを一切使わない純米酒醸造蔵となる。2019年より農業法人を設 ...
「酒は天下の太平山」家伝生酛の魅力【太平山】小玉醸造‐秋田県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第181回目の当記事では、秋田県潟上市(かたがみし)の小玉醸造(こだまじょうぞう)を特集します。 太平山流の技、心温まる旨み ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 明治12年(1879年)に秋田県中央部の飯塚で創業。伝統的な生酛仕込みを続け、現在でも「家伝生酛」として太平山流の酒造りの基本技となっています。 昭和9年(1934年)に全国品評会で第1位を獲得するなど鑑評会の受賞多数。近年ではインターナショナルワ ...
「酔うため、売るための酒ではなく、味わう酒を求め」【獺祭】旭酒造‐山口県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第177回目の当記事では、山口県岩国市(いわくにし)の旭酒造(あさひ)を特集します。 味わい豊かな酒が紡ぐ楽しい生活の一杯 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 大量販売の論理から生まれた酔えばいい、売れればいい酒ではなく、おいしい酒・楽しむ酒を目指してきました。 何より、酒のある楽しい生活を提案する酒蔵であり続けたいと考えています。 生活の、一つの道具として楽しんで頂ける酒を目指して、「獺祭」(だっさい)を ...
地の米、水、技で醸す本物の山口地酒蔵【五橋】酒井酒造‐山口県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第167回目の当記事では、山口県岩国市(いわくにし)の五橋(ごきょう)を特集します。 錦帯橋の調べ、地元の米・水・人が醸す高質な酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 明治4年(1871年)創業。「五橋」の酒名は、錦川にかかる五連の反り橋「錦帯橋」にちなんで命名。 以来、山口県を代表する銘酒として愛飲されてきました。「山口県の地酒」であるために地元の米・水・人にこだわったその酒は、軟水仕込み特有の決め細やか ...
様々な料理とシーンに共鳴し、人々に寄り添う酒造り【長門峡】岡崎酒造場-山口県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第104回目の当記事では、山口県萩市(やまぐちけんはぎし)の有限会社岡崎酒造場(おかざきしゅぞうじょう)を特集します。 長門峡という酒名は景勝地の名前に由来 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 山口県の維新の街城下町萩市(旧川上村)の山の中、景勝地「長門峡(ちょうもんきょう)」の近くで大正13年より創業しておりましたが、昭和45年阿武川ダムの建設により、萩市の上流にあたる現在地に移転しました。 長門峡という ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第93回目の当記事では、山口県岩国市(やまぐちけんいわくにし)の八百新酒造(やおしんしゅぞう)株式会社を特集します。 米蔵を酒蔵に変えて酒造りを始めた ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業1877年(明治10年)。江戸時代には、山口県の東部を流れる”錦川”が瀬戸内海に注ぎ込む河口近くに岩国藩の米蔵がありました。明治維新以後、藩からそこを譲り受けた我々の創業者が米蔵を酒蔵に変えて酒造りを始めました。 酒蔵 ...
次代に輝く究極の日本酒へ、挑戦をつづける酒造り【金冠黒松、村重、eight knot】村重酒造-山口県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第62回目の当記事では、山口県岩国市(やまぐちけんいわくにし)の村重酒造(むらしげしゅぞう)株式会社を特集します。 硬水と軟水が使い分けられる酒造で、酒造りの幅が広がる ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 昭和26年に明治初期創業の名門・森乃井酒造株式会社を継承した当酒造は、日本三名橋のひとつ「錦帯橋」の上流約5kmにさかのぼった山あいの寒冷清涼な土地で、豊富な水を利用した酒造りを行なっております。 仕込み ...
徳島県
五感で感じ楽しみながら造る酒造り【芳水】芳水酒造有限会社-徳島県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第26回目の当記事では、徳島県三好市(とくしまけんみよしし)の芳水酒造(ほうすいしゅぞう)を特集します。 日本酒一筋の酒造り。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 名水百選の御神水が湧く霊峰・剣山に連なる山地を南に背負い、北に四国の長流・吉野川を眼下に、その先には阿讃山脈を望む山紫水明の山峡に質朴な芳水の酒蔵はあります。 徳島県の北西部に位置し、温暖な四国には珍しく日照時間が短くて冬季の冷え込みも厳しく、酒 ...
香川県
1789年創業、金刀比羅宮御神酒醸造元【金陵】西野金陵‐香川県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第237回目の当記事では、香川県仲多度郡(なかたどぐん)の西野金陵(にしのきんりょう)株式会社を特集します。 金刀比羅宮の誇りの御神酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1789年八代当主嘉右衛門が金刀比羅宮(こんぴらさん)の麓で酒造りを始めたのが第一歩です。以来、金陵は、讃岐の金刀比羅宮の御神酒として地元の人々や金毘羅詣での方々に広くご愛飲いただいています。 ―代表銘柄は? 「煌金陵 純米大吟醸酒」香川 ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第188回目の当記事では、香川県小豆郡(しょうずぐん)の小豆島酒造を(しょうどしましゅぞう)特集します。 小さな島の誇り。伝統と個性が織りなすお酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 小豆島酒造は、美味しい地酒を目指して観光地小豆島に渡ってきた小さな酒蔵です。 地元小豆島の人々に支えられながら、伝統を守りながらも個性を大事に小豆島の地酒を守ります。 ―代表銘柄は? 「小豆島の輝 大吟醸」 小豆島の輝 大吟醸 ...
郷土を愛する心が「綾菊」の原点です【綾菊・国重】綾菊酒造-香川県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第127回目の当記事では、香川県綾歌郡(あやうたぐん)の綾菊酒造(あやきく)を特集します。 郷土を愛する心を原点に ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 綾菊酒造は綾川のほとりにあり、清流綾川の伏流水、天皇ご即位献上の栄誉ある良質の讃岐米、阿讃山脈の北麓に位置した冬季寒冷な気候と好条件に恵まれたこの地で古くより酒造りを行っております。 綾菊の命名は、この綾川とこの地で酒造りを始めた酒部綾黒丸より綾を取り、菊の ...
愛媛県
見てろよ、次の百年を~雀の酒造り伝説【雪雀】雪雀酒造‐愛媛県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第218回目の当記事では、愛媛県松山市(まつやまし)の雪雀酒造(ゆきすずめしゅぞう)を特集します。 首相が勧めた銘「雪雀」 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業大正四年(1915年) 酒銘は日本の昔話「雀の酒造り」があるのにちなんで『雀正宗』と名付けられました。 その後、昭和になり初代蔵元と親交のあった当時の首相 犬養毅氏 より『雪雀』という銘にするよう勧められ今に至ります。 “雪”は昔から豊年の瑞兆と ...
「暖簾を守るな、暖簾を破れ」の教えを体現する、道後唯一の酒蔵【仁喜多津、道後蔵酒】水口酒造‐愛媛県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第146回目の当記事では、愛媛県松山市(まつやまし)の水口(みなくち)酒造を特集します。 伝統と革新が息づく、道後温泉唯一の造り酒屋 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 愛媛・松山・道後、創業明治28年(1895年)、日本最古の温泉として全国的に知名度がある「道後温泉」地区唯一の造り酒屋です。 創業家に伝わる「暖簾を守るな、暖簾を破れ」の想いを胸に、日本酒の酒蔵でありながら、ビール事業にも携わる等、常に新し ...
自分の肌で感じるものが真実だと考え、手造りにこだわる酒造り【日本心、媛一会】武田酒造株式会社-愛媛県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第28回目の当記事では、愛媛県西条市(えひめけんさいじょうし)の武田酒造(たけだしゅぞう)を特集します。 自然の酒蔵に変わると言われる地域。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 四国は愛媛、愛媛県の東部にあります西条市に武田酒造株式会社がございます。眼下に瀬戸内海を臨み、背後には西日本最高峰の石鎚山、酒造りの季節になりますと山脈よりの冷たい風が吹きおろし平野全体が冷やされ、自然の酒蔵に変わると言われる地域で ...
データと人の手で進化する酒造り【梅美人、鷹雄】梅美人酒造株式会社-愛媛県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第8回目の当記事では、愛媛県八幡浜市(えひめけんやわたはまし)の梅美人酒造(うめびじんしゅぞう)を特集します。 伊方杜氏が造りだす日本酒 梅美人 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 梅美人酒造は大正5年愛媛県八幡浜市の地に「上田 梅一」が創業し105年の歴史を経て現在に至ります。明治期には「伊予の大阪」とよばれ、港を利用した商業が盛んでした。その背景には、明治3年に宇和島藩が民間につくらせた八幡浜商社の伝統 ...
高知県
心の栄養となれるよう“やさしさを持った”酒を目指す【安芸虎】有限会社有光酒造場-高知県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第37回目の当記事では、高知県安芸市(こうちけんあきし)の有光酒造場(ありみつしゅぞうじょう)を特集します。 小さい蔵独自の「味わい深い酒」を追求 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 有光酒造場は温暖な地、高知県の小さな酒蔵で、安芸市清流・赤野川のすぐ側に位置します。清流赤野川水系の水は柔らかな味で、ふくらみと優しさのある酒に適しています。 創業は明治36年(1903年)。創業者の有光伊太郎は、三菱の創始者 ...
福岡県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第210回目の当記事では、福岡県筑紫野市(ちくしのし)の大賀酒造(おおがしゅぞう)を特集します。 宝満山の恵み、筑紫野の酒蔵の物語 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 私どもの蔵は、福岡市のベッドタウンとして成長を続けている、筑紫野市の二日市にございます。二日市は江戸時代に宿場町として栄え、黒田藩が二日市に本陣を設けた地でもあります。 大賀家は黒田藩主から酒造りを任され、太宰府を裾野にもつ宝満山の伏流水を使 ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第201回目の当記事では、福岡県大川市(おおかわし)の若波酒造(わかなみしゅぞう)を特集します。 若さと伝統、波に乗って100年 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1922年創業。100周年を迎えたばかりの酒蔵です。 蔵は九州一の大河「筑後川」の傍に位置し、その若々しい波の姿より、若い波を起こし続けよと銘を受けました。 弟が当主を務め、姉の同期生が杜氏を、姉は若手の育成や蔵の循環といった蔵創りを担う3本の ...
筑後川の恵みを受けて、創業者の魂と技を受け継ぐ丹念な酒造り【筑紫の誉】筑紫の誉酒造-福岡県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第45回目の当記事では、福岡県久留米市(ふくおかけんくるめし)の筑紫の誉酒造(ちくしのほまれしゅぞう)株式会社を特集します。 筑紫野平野をうるおす筑後川の恵まれた土地で丹念な酒造りに専念 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 筑紫の誉酒造は福岡県久留米市城島町にあり、九州最大の穀倉地帯である筑紫平野をうるおす筑後川が流れています。この豊かな自然に恵まれた中で酒造りをおこなっています。創業明治30年以来、創業者 ...
独自の旨さの創造を通して、旨いの先にある幸せをお届け【杜の蔵、独楽蔵】株式会社杜の蔵-福岡県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第44回目の当記事では、 福岡県久留米市(ふくおかけんくるめし)の杜の蔵(もりのくら)を特集します。 粕取り焼酎造りで創業 。 その数年後、今となっては主力となった日本酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 地元の久留米市三潴町(みずままち)は九州一の河川である筑後川の流域に広がる筑後平野のほぼ中心に位置しています。 全国的にはあまり知られていませんが、福岡県は稲作が盛んなだけでなく、古くから ...
豊かな自然環境の中、伝統の技で酒造り【無法松、舞姫】無法松酒造有限会社-福岡県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第25回目の当記事では、福岡県北九州市(ふくおかけんきたきゅうしゅうし)の無法松酒造(むほうまつしゅぞう)を特集します。 地方創生の成功モデルの1つになりたい 。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1877年(明治10年)に現在の地(国定公園でもある平尾台のふもと)にて創業。紫川の支流・東谷川の上流にあたり、豊かな自然環境の中、伝統の技で酒造りを続けています。 その中で時代にあった商品展開ができないか日々 ...
日本酒と焼酎の文化がサスティナブルに連鎖する酒造り【繁桝、箱入娘、麹屋、博多一本〆】株式会社高橋商店-福岡県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第13回目の当記事では、福岡県八女市(ふくおかけんやめし)の高橋商店(たかはししょうてん)を特集します。 継承の技を守り、さらに研鑽 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 高橋商店の歴史は江戸時代享保2年(1717年)に、初代高橋六郎右衛門が米どころ八女で造り酒屋を開業するところから始まります。その後、九代目竹吉による基礎固めや十代目繁太郎の会社組織への改組など様々な変遷を経て、今日の十九代目に至ります。 弊 ...
佐賀県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第152回目の当記事では、佐賀県鹿島市の光武(みつたけ)を特集します。 伝統を守り、品質を向上させる酒蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業は1688年と非常に歴史の長い蔵です。 光武酒造場のある佐賀県鹿島市浜町は、江戸時代から酒造りの盛んな地域で、数ある酒蔵の中でも光武酒造場は「伝統の中からの革新」を合言葉に、昔ながらの酒造りの伝統は守りながらも一つ一つの製品の品質向上のため絶え間のない努力を続けて ...
人・米・造りが一体となって良酒を醸す。米から育てる酒造り【東一】五町田酒造株式会社-佐賀県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第40回目の当記事では、佐賀県嬉野市(さがけんうれしのし)の五町田酒造(ごちょうだしゅぞう)を特集します。 古くから良質な水田が広がり、稲作に適した地域 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 当社は、有明海にほど近い佐賀県西南部に位置し、三方を山に囲まれた盆地です。寒暖の差が激しい嬉野市塩田町(しおたちょう)では稲作をはじめとする農業が盛んです。酒蔵がある”五町田”地区では、古くから良質な水田が広がり、稲作に ...
一に米、二に水、そして技。優しさの感じられる酒造り【聚楽太閤、瀧】鳴滝酒造株式会社-佐賀県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第38回目の当記事では、 佐賀県唐津市(さがけんからつし)の鳴滝酒造(なるたきしゅぞう)を特集します。 モットーは「一に米、二に水、そして技」 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 昭和49年創業。3酒造蔵の企業合同により設立されました。前身を溯れば300年を超える歴史を有します。 新たな蔵を設立する際、徹底的にこだわったのが「水」でした。かつて豊臣秀吉がその水を用いて千利休に茶を点てさせたと伝わる ...
酵母、麹菌の能力を最大限に引き出す酒造り【東鶴】東鶴酒造株式会社-佐賀県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第34回目の当記事では、佐賀県多久市 (さがけんたくし)の東鶴酒造(あずまつるしゅぞう)を特集します。 原材料と製法にこだわりをもって少量のお酒を家族ぐるみで醸しています。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1830年創業。佐賀県の真ん中に位置し、山々に囲まれた土地である多久市で代々日本酒を製造販売しております。元々は市内に7、8軒あった酒蔵もすべて廃業し、弊社も平成元年を境に休業していましたが、平成21 ...
多良岳山系の伏流水、佐賀県産米を使った吟醸造り【幸姫】幸姫酒造株式会社-佐賀県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第23回目の当記事では、佐賀県鹿島市(さがけんかしまし)の幸姫酒造(さちひめしゅぞう)を特集します。 日本三大稲荷のひとつ、祐徳稲荷神社の御神酒醸造元。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 幸姫酒造株式会社は九州の佐賀県鹿島市にあります。佐賀県は古くから米の生産が盛んで、それに伴い清酒の製造も盛んでした。鹿島市もその例にもれず酒造業が盛んな地域です。 1934年に創業。現在は食中酒として楽しめる純米酒の製造 ...
長崎県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第269回目の当記事では、長崎県新上五島町(しんかみごとうちょう)の五島灘酒造(ごとうなだしゅぞう)を特集します。 五島初の焼酎蔵と共に歩む伝統と想い ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 「100年先も、よりよい島の風景が残り栄えて欲しい」そんな願いを込めて2007年、先代社長は五島で初めての焼酎蔵を立ち上げた。 「農業は、人間の原点である」という考え方から、島の生産者と協力し原材料である甘藷栽培から焼酎を ...
「佐世保の手造り地酒、歴史と伝統の息吹」【梅ヶ枝】梅ヶ枝酒造‐長崎県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第176回目の当記事では、長崎県佐世保市(させぼし)の梅ヶ枝酒造(うめがえ)を特集します。 200年の歴史を超えた味わい ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業天明七年(1787)江戸中期、11代将軍家斉の時代、時の大村藩主・大村純鎮公より「梅ヶ枝(うめがえ)」の名を賜る。 豊かな自然と地下300メートルからの名水に恵まれ、以来200有余年、米づくりから酒づくりまで日々こだわりの手づくりをしています。 今 ...
平戸の風土と代々受け継がれてきた酒造りの技【福鶴、長﨑美人、福田、じゃがたらお春、かぴたん】福田酒造-長崎県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第51回目の当記事では、 長崎県平戸市 (ながさきけんひらどし)の 福田酒造(ふくだしゅぞう)株式会社を特集します。 「酒造りは、心でつくり、風が育てる。」 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 当社のある平戸市は長崎県北西部の位置し、長崎県と九州本土の市としては、最西端に位置しています。平戸の歴史は古く、日本で最初の海外貿易港として、ポルトガル・オランダ・イギリスとの交易が始まり、西の都として繁 ...
世界に轟く一杯目、世界を見据えた酒造り【よこやま】重家酒造横山蔵-長崎県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第47回目の当記事では、長崎県壱岐市(ながさきけんいきし)の重家酒造(おもやしゅぞう)株式会社の横山蔵(よこやまぐら)を特集します。 世界に轟く「酒」を醸すために設計された横山蔵で造る日本酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 重家酒造の横山確蔵は、1924年(大正13年)に長崎県壱岐島に日本酒蔵・焼酎蔵を創業し、現在は、四代目である横山雄三が代表 兼 焼酎杜氏、弟の横山太三が専務取締役 兼 日本酒杜氏とし ...
島全体がパワースポットと言われる壱岐島で作られた焼酎【壱岐っ娘、壱岐の島】壱岐の蔵酒造株式会社-長崎県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第36回目の当記事では、長崎県壱岐市(ながさきけんいきし)の壱岐の蔵酒造(いきのくらしゅぞう)を特集します。 現代の製法は、江戸時代の時代背景に合わせて確立してきた ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1984年に壱岐島内の2〜300年の歴史ある6蔵が全国に壱岐焼酎を全国に知っていただく為に合併しました。 2010年にさらなる飛躍と壱岐焼酎の発展を願い「壱岐の蔵酒造株式会社」と社名及び組織変更を致しておりま ...
伝統の味わいを継承し革新的な視野で取り組む酒造り【杵の川、黎明】株式会社杵の川-長崎県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第31回目の当記事では、長崎県諫早市(ながさきけんいさはやし)の杵の川(きのかわ)を特集します。 良か人と良か酒を育む蔵 。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 天保10年(1839年)長崎県東彼杵町で清酒恵美福の醸造元「丁子屋醸造」として創業した酒蔵です。その後昭和55年に、丁子屋醸造、黎明酒造を中心に4つの蔵が一つになり「清酒杵の川」が誕生しました。 「良か人と良か酒を育む蔵」をモットーに、地元の食に合 ...
伝統技法のはねぎ搾り、花酵母の特性を生かす酒造り【萬勝】合資会社吉田屋-長崎県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第30回目の当記事では、長崎県南島原市(ながさきけんみなみしまばらし)の吉田屋(よしだや)を特集します。 今では数少なくなった「はねぎ搾り」の製法 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 大正6年創業。名水で知られる長崎県島原半島の南部に位置する南島原市有家町にあります。雲仙の伏流水が湧き出る自家井戸の水を仕込み水に使用して、東京農大花酵母研究会の花酵母を使って醪(もろみ)を仕込み、今では数少なくなった「はねぎ ...
熊本県
飲んで旨いお酒、飲み手の心を豊かにするお酒を【泰斗、朱盃】千代の園酒造‐熊本県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第249回目の当記事では、熊本県山鹿市(やまがし)の千代の園酒造(ちよのそのしゅぞう)を特集します。 純米酒の先駆け、米にこだわる酒造り ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 千代の園は明治29年(1896年)創業の酒蔵です。米問屋を営んでいた初代が、米へのこだわりから酒造りを始めました。戦後の昭和43年(1968年)、普通酒が主流となっていた時代に全国に先駆けて純米酒造りに取り組み、その純米酒を『朱盃』と名 ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第208回目の当記事では、熊本県上益城郡(かみましきぐん)の通潤酒造(つうじゅんしゅぞう)を特集します。 「寛政蔵」からの新たな息吹 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 明和7年(1770年)創業。代々の細川公がお泊まりになる御成りの間があり、明治10年の西南の役では西郷隆盛が宿泊し本陣となりました。熊本地震で大きなダメージを受けた熊本で一番古い「寛政蔵」リノベーションし、おしゃれな酒蔵カフェとして生まれ変 ...
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第199回目の当記事では、熊本県球磨郡(くまぐん)の那須酒造場(なすしゅぞうじょ)を特集します。 昔ながらの道具と技、球磨の心。 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 大正6年に創業で家族経営の小さな蔵元です。四方を山に囲まれた秘境・熊本県人吉球磨盆地に移り住んだ先祖が、寒暖差が激しいこの地特有の自然が生み出した米と清水を使い、焼酎造りを開始しました。初代の那須虎治より始まり現在4代目ですが、創業当時の製法を ...
人生最後の乾杯にふさわしい酒造り【七歩蛇・花雪・小国蔵一本〆】河津酒造-熊本県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第129回目の当記事では、熊本県阿蘇郡(あそぐん)の河津酒造(かわづ)を特集します。 手で作り上げる究極的に美しい日本酒を目指している蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 河津酒造は、創業の昭和7年、熊本県の中でも新しい酒蔵です。 高度経済性成長からバブル期までのピーク時に2,000石程度の造りを行なっておりました。日本酒離れや他のアルコール類のブーム、人口減、味覚の変化と日本酒の技術のミスマッチングを原 ...
大分県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第192回目の当記事では、大分県宇佐市(うさし)の久保酒蔵(くぼしゅぞう)を特集します。 水に恵まれた宇佐の地で、130年以上続く老舗の焼酎蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 大分県の県北の地、宇佐市長洲に寛政元年(1789年)に創業した蔵です。製造場はかつて当時の氏神様であります。 貴船神社の境内にあり水神様を祭っている由緒ある場所で今も水に恵まれた環境にある場所です。2007年より焼酎製造蔵として現 ...
瀬戸内の小さな酒蔵で、彩りゆたかなお酒をつくる【防長鶴】山縣本店‐山口県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第183回目の当記事では、山口県周南市(しゅうなんし)の山縣本店(やまがたほんてん)を特集します。 四季折々の香りが息づく小さな酒蔵 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 1875年(明治8年)創業。瀬戸内海の、旧山陽道の面した小さな酒蔵です。 寒い冬に日本酒を仕込み、初夏には収穫したての梅の実で梅酒を仕込みます。秋には、堀りたてのさつまいもが入ってきます。さつまいもを蒸して、濃醇な芋焼酎を造ります。一年を通 ...
大分でしか造れない日本酒を目指して、気候風土を活かした酒造り【豊潤】小松酒造場‐大分県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第179回目の当記事では、大分県宇佐市(うさし)の小松酒造場(こまつしゅぞうば)を特集します。 150年歴史を超えて蘇る酒 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 大分県北部に位置する小松酒造場は、明治元年に創業しました。蔵のある宇佐市長洲地区は、酒造りに適した水と、宇佐平野でとれる米、冬の季節風という恵まれた環境で酒造りを行ってきました。 昭和63年に製造を休止しましたが、平成20年に6代目の帰省を機に製造を ...
大分県で最初の生酛造り【久住千羽鶴】佐藤酒造株式会社-大分県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第10回目の当記事では、大分県竹田市(おおいたけんたけだし)の佐藤酒造(さとうしゅぞう)を特集します。 大分県竹田市久住町にある唯一の清酒蔵 画:詫間文男先生 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 創業1917年(大正6年)、大分県南西部に位置する竹田市久住町にある唯一の清酒蔵になります。標高が600mと高い位置にあり年間を通じて冷涼な気候と、久住山からの柔らかい伏流水を仕込み水に使用しております。代表銘柄の ...
沖縄県
戦後、泡盛復興に尽力した蔵元【咲元復刻30度、蔵波】咲元酒造-沖縄県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第99回目の当記事では、沖縄県国頭郡(おきなわけんくにがみぐん)の咲元酒造(さきもとしゅぞう)株式会社を特集します。 琉球王府のお膝元である首里にルーツを持ち、100年余りの歴史を有する酒造所 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。琉球王府のお膝元、首里三箇(崎山・赤田・鳥堀)にルーツを持ち、明治35年創業以来、味ひとすじで100年余りの歴史があります。時代のあおりで廃業寸前だったところ、観光施設琉球村との資本 ...
地元唯一の酒造所として伝統を守りながら常に新しい挑戦を進める酒造り【美しき古里、千年の響、今帰仁城】今帰仁酒造-沖縄県
地域で愛される酒蔵の銘酒に着目し、酒蔵からの生の声と和酒情報を読者の皆様にお届けする連載企画。第70回目の当記事では、沖縄県国頭郡(おきなわけんくにがみぐん)の有限会社今帰仁酒造(なきじんしゅぞう)を特集します。 貯蔵方法や熟成によって味わいが大きく変化する琉球泡盛 ―酒蔵の歴史や地域について教えて下さい。 沖縄本島北部に位置する今帰仁村は、那覇から車で約2時間北上した、手つかずの自然や沖縄の原風景が残る場所です。 琉球王朝時代の名残を残した世界遺産「今帰仁城跡」をはじめ、毎年1月末の桜の開花時期には多く ...
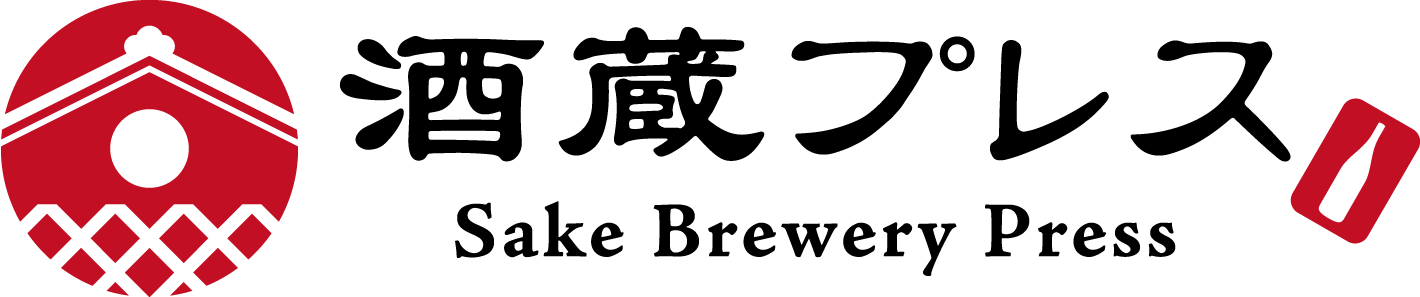























1-202x150.jpg)
-202x150.jpeg)



























R20511-202x150.jpg)










-202x150.jpg)

















































































































































-202x150.jpg)




















-202x150.jpg)


















