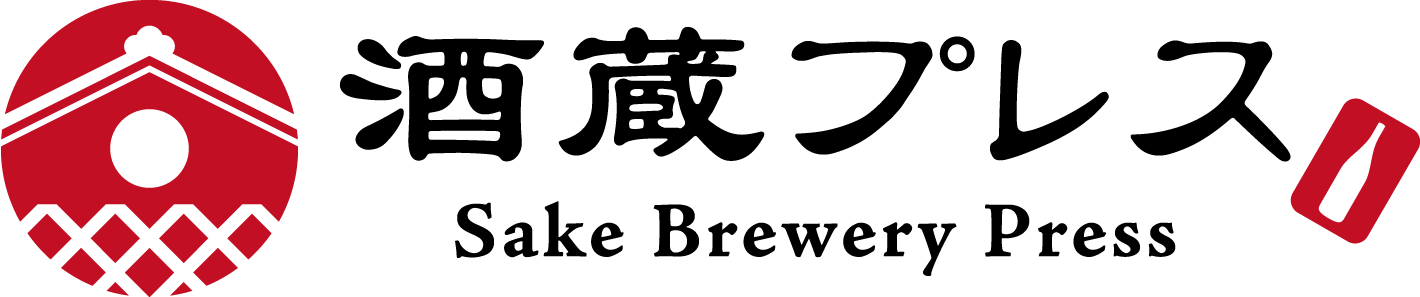酒匠・日本酒学講師としてもご活躍されている石黒建大さんの「日本酒の生酛系造りの手法【丹波流(灘)と能登流(能登・加賀)】の違いによる味わいの特性および販売市場特性に関する研究」について、酒蔵プレス独占で4回にわたり研究内容を特集いたします!今回が最終回です!
日本酒を普段から飲んでいて生酛造りについてよくご存知の日本酒ファンや日本酒を飲み始めて生酛造りをあまり知らない日本酒初心者にも新たな発見になる内容です。
「前回の特集」を読んでいない方はこちらから
-

-
【連載】日本酒の生酛系造りの手法の違いによる味わいの特性(3)
酒匠・日本酒学講師としてもご活躍されている石黒建大さんの「日本酒の生酛系造りの手法【丹波流(灘)と能登流(能登・加賀)】の違いによる味わいの特性および販売市場特性に関する研究」について、酒蔵プレス独占 ...
続きを見る
灘酒を中心とした丹波杜氏の酒造りと加賀酒を中心とした能登杜氏
灘酒の酒造りを行う杜氏は、主に丹波杜氏である。1755年(宝暦5年)篠山曽我部(現在の篠山市日置)の庄部右衛門が、池田の大和屋本店の杜氏となったのが、その起源とされている。
丹波杜氏の供給地は、主として多紀郡現篠山市の村々で、厳しい生活の中、農閑期の「百日稼ぎ」と言われる「出稼ぎ(冬季の季節従業員)」で生活の糧をえており、江戸時代には酒造りのために伊丹や池田に出稼ぎしていた。元禄期(1688~1703年)の伊丹の酒は丹波の蔵人が作り出す銘酒であり、「剣菱」や「男山」等、現在のほとんどの灘酒の銘酒を作り上げただけでなく、全国に指導に出かけ、地方の銘酒の原型を作った。
300年の長い歴史と伝統とに育まれた匠の技、その匠の技を磨く勤勉さがあり、次世代の造り手を育てる能力に長けている事が、現代でも丹波杜氏が日本を代表する酒造りの杜氏集団たるゆえんである。
丹波流の酒造りは、宮水のように硬水で仕込む方法で、生酛の製造工程において半切り桶を使用する工程の期間が短く、育成に場所をとることが少なく、他の流派よりも工業制手工業的(マニュファクチャー)であり、灘の酒造りには好適であった。

一方、能登杜氏とは、江戸後期より能登半島の先端に属する珠洲市周辺を発祥とする杜氏集団である。耕作面積が非常に狭く、特産品もほぼなかったので、農業や漁業の閑散期である冬季に、畿内地方(特に山城現京都府や近江現滋賀県)に酒造りの出稼ぎするようになった。
他の地域の杜氏や蔵人集団とは異なり、江戸時代初期より独自の酒造技術を伝承していったので、能登衆と呼ばれ、他の地域の出稼ぎのものとは、はっきりと区別されていた。技能集団として確立されたのは、江戸後期の文化・文政年間(1804~1829年)とされ、この時期は江戸期で最も景気の良い時期であり、創業する酒蔵も全国的に非常に多かった。
その後、1906年(明治37年)に珠洲郡杜氏組合が設立され、1922年(大正10年)に能登杜氏組合に改称された。1903年(明治34年)8月に杜氏組合設立に伴う記念行事として初の酒造講習会が開催されたといわれている。この講習会が「能登流酒造り」のきっかけとなり、能登杜氏の酒造技術は飛躍的に向上したとされている。また、明治時代から能登杜氏の技術を磨くための独自の品評会が明治37年より現在まで毎年開催されており、農口尚彦杜氏をはじめとして優秀で有名な杜氏を複数輩出している。
能登杜氏の最盛期は昭和2年と言われていて、この年402人の杜氏と1644人の蔵人が全国各地へ出稼ぎに出た。現代でも全国各地の地方の銘酒蔵で能登杜氏が活躍しているが、実は70人前後と後継者不足が問題となっている。能登流の酒の特徴として、味の濃い酒質の製成酒と一般に言われていて、特に吟醸酒造りにおいて多くの銘酒を輩出しており、吟醸造りにおいては能登流が一番ともいわれている。
なお、杜氏の流派で丹波杜氏と能登杜氏を区分けした場合、丹波流は丹波新流灘流と丹波古流に分かれていて、能登流は丹波古流と但馬地流の流派に属し、元々は同じ流派から派生している。
京阪神の食文化の結晶である灘酒と加賀百万石の食文化の結晶である加賀酒の違い
江戸や加賀の食文化を研究してみて、江戸時代初期の様に、経済的に余裕が無く、生活の安全が保障されない状況下においては、食文化も酒文化も発展性に乏しく、生きていく為の日々の食事を如何に入手するのかということで、自身で食物の生産を行わなかればならなかった。そのため、酒については「日々の生活の苦しさを紛らわせるためのツール」として存在している部分もあったように感じる。決して食卓に華やかさを演出する訳では無く、食事の味わいをより美味しくする物でも無かった。
一方で、室町時代後期から戦国期、安土桃山期においては、ハイクラスの貴族や武家などの内政や貴族の荘園造りのために、「人を集めるツール」として酒が用いられ、それと同時に酒造りの技術が磨かれた結果、現代清酒の基礎の技術となる部分が磨かれ、一定レベルの高品質の酒造りに繋がり、結果的に幻の銘酒である天野酒や加賀菊酒が天下の銘酒として世の中に登場し、江戸初期における南都諸白の酒造りにまで発展したと考えられる。
その後、大阪の陣を経て実質的な戦国期の最後の合戦となったのは、三代将軍徳川家光公の頃に発生した島原の乱である。その後、四代将軍徳川家綱公の頃に最後の幕府を転覆させるための油井正雪の乱が起こったが、1681年からの五代将軍徳川綱吉公の頃には、江戸幕府の統治基盤、経済基盤が安定し、元禄文化と呼ばれる一般の町人にとって初めてとも言える好景気の世の中になった。

そのような中で、全国の年貢米と特産品の集積地として発展した大坂市場を中心に食文化の発展がみられ、世界的にみても経済成長率の高かった日本において初期の資本主義経済が形成されていった。
その結果、享保期以降大坂では、昆布出汁と薄口醤油を中心に日本を代表するような食文化が形成され、その市場競争の中で揉まれた灘酒がやがて天下の銘酒として江戸市場まで席巻し、その後日本を代表するナショナルブランドと言われるまでに発展していって、現代にいたるまで灘酒のブランドが揺るぎなきものとなった。
日本を代表するナショナルブランドになった灘酒と日本で最初にGIを獲得した加賀酒

時代が進み、八代将軍徳川吉宗公でお馴染みの暴れん坊将軍の頃になると、幕政は更に安定し、世の中の治安に関しても安定度を増した。その後、田沼意次公の時代には、一般の庶民間に置いても伊勢参りをはじめとする旅が行われるようになり、宿場において、旅客に提供される郷土料理や地の名物料理が確立され、江戸時代の旅行業者にあたる御師の宿で提供するための高品質の酒が、東海道を中心に地方でも造られるようになっていった。
吉宗公の享保期以降においては、ハレの日のための一定以上の高品質な食や酒が市場に求められるようになったと考えられる。
世界最大の都市であった江戸はもちろんのこと、現代においても東京のGDPは世界一である市場において、当時の酒処であった上方間の酒造り競争は、熾烈を極め、灘流の酒造りを基にした灘酒が、市場間での競争に勝ち残り、現代にもつながる灘酒の絶対的なブランド力の確立に成功したと考えられる。
何故ここまで灘流の酒造りが成功したのかというと、江戸に各酒蔵の事実上の支社に当たる卸問屋を設立させ、その卸問屋に重点的に自社の酒を卸した事と、高品質の大量生産に適した灘流の寒造りの生酛造りの技術を確立させ、他所には無いマニュファクチャーによる酒造りが行われるようになった事や、19世紀に灘の代名詞である宮水が発見されてから、その宮水を軸とした中硬水による酒造りの技術が確立された事だと考えられる。
一方で加賀酒に関しては、戦国期に浄土真宗石山本願寺派一向宗により加賀の国が実質支配下におかれていた際に、一向宗の庇護(ひご)の下で、堺の商人の菊屋と米屋が進出し、畿内の先進的な酒造りの技術を用いて、一向宗の本拠地である鶴来において菊屋が加賀菊酒を造っていたと言われている。
他にも諸説があり、豊臣政権下の桃山時代において前田利家公が加賀に入った際に、尾張の国から利家公専用の酒を造らせる為に「やちや酒造(加賀鶴)」の創始者である神谷内屋仁右衛門を移住させる等、早い時期から酒造りの先進地である。また、加賀百万石の経済力を背景に独自の進化を遂げた加賀料理と共に日本酒に関しても独自の進化を遂げ、上方から酒造りの専門家である蔵人を招くなどして、先進技術の取得に関しても早い段階から非常に熱心に取り組んでいた。また現代においても石川県は、日本を代表する能登地方の加賀杜氏が存在し、日本を代表する銘醸地である白山地区の加賀菊酒が全国初の日本酒の原産地呼称であるGIを獲得するなど、石川県の特産品として銘酒を数多く輩出している。
灘酒は、酒の大消費地である京阪神と江戸の市場で、年貢の集積地の大坂の米を背景に、常に最新の技術を開発しながら江戸期には工業制手工業を確立し、明治期以降は丹波杜氏の技術と大資本を背景にした大規模な工業化や酒造りの先進技術の開発により日本を代表する銘醸地となり、大手の酒蔵の集積地となっている。
一方で加賀酒は、江戸期には日本一の加賀百万石の経済力と先進的な加賀料理を背景に独自の酒造りの技術的進化を遂げ、明治期以降も能登杜氏組合を中心に杜氏間の競争により独自の進化を遂げ、現代においても金沢酵母の開発や石川門等の独自の酒米の開発や県の支援を背景にした大資本にはないソフト面を中心とした技術開発により、日本を代表する銘醸地として現代においても日本酒造りの先進地となっている。
経済、食、歴史、文化この研究のまとめ
今回は、丹波杜氏の灘流の生酛造りと能登杜氏の加賀流の山廃造りにおいて、味わいの違いを中心に研究を進めてきたが、食文化と酒文化、経済、工業、商業文化を多角的に検証した結果、一般に言われる日本酒の通説は必ずしも正解と言えない部分もあり、端的に説明をする場面では正解であるという考えに至った。
しかし、実際に酒を取り扱うプロの方や日本酒の資格保持者、ソムリエの方々に関しては、通説で酒を語るのではなく、食、酒、食べ物と酒の組合せ、経済、歴史、文化等の多角的な視点から、酒文化そのものを掘り下げて考え、自分自身で研究する事で消費者の方々に本当の意味で価値のある一杯の日本酒を自分自身の言葉で提供する事が出来るようになって欲しい。本当に価値のある一杯の日本酒を、自分自身の言葉や考え方で提供できて初めて、本当の意味での「日本酒のプロ」という事が出来るのではないかと私は考えている。
最も、実際の現場でそのように日本酒を提供する事は非常に難しい事ではあり、一杯の日本酒の価値を消費者の方々に理解して貰う事は非常に難しい事でもあるが、大阪の「づぼらや」の「ひれ酒」のように、店としての独自の文化と歴史、考え方を軸に日本酒を提供できていたお店も稀に存在する。

また酒造りにおいては、灘流の生酛造りのお酒は「ふくよかさと味わいの深みを持ちながら後味がシャープでキレが良くスッキリした味わいの傾向」が有る事に対して、加賀流の山廃造りのお酒は「ふくよかで滑らかで、厚みのある旨味を持ち、後味のキレの良い傾向」が見られる。
灘流の日本酒に関しては、京阪神のマーケットで絶対的な強さ(実際に1990年代前半において灘酒の大阪市場での日本酒のシェアは90%を超えていた)を追求した結果、大阪や京都の食卓に合う傾向の味わいとなり、和食の料理人の多くが、以前は上方で修業を積む傾向が多かった事を考えると、京阪神や京浜方面で日本において灘酒のブランドが確立したのは当然である。一方で加賀流の日本酒に関しては、加賀百万石や一向宗本願寺派が持っていた日本のどの地域にもなかった圧倒的な経済力や食文化、日本海の豊かな食材を背景に、加賀料理に合う日本酒が、現代の加賀流の山廃造りの日本酒のようなふくよかさと厚みのある味わいになるのは自然な流れである。
一方で、市場や消費者に対して、時代や経済状況、食卓の変化に合わせて提供するお酒を変化させる必要がある。そういった変化に対して、酒造りの文化を活かしながら対応したのが、灘流や加賀流の生酛系の日本酒造りであり、現代の日本のマーケットにおいても根強く受け入れられている。
必ずしも灘流の生酛の在り方が、生酛本来の味わいでもなければ、加賀流の山廃酛のお酒が生酛本来の味わいとも言えない。そして、日本酒の発展過程において、これまで先人の方々の百試千改の努力の結果、現代における完成度の高い日本酒に発展してきたことから、生酛系の造りの日本酒だけが伝統的な味わいの日本酒と考えるのは正解とは言えない事が、今回の研究の成果報告である。
その要因を深く知り、地域によって比較し、そして現代の日本酒を飲み、比べることで、日本酒がいかにありがたいものであり、日本酒造りがいかに奥深いものであるかを知ってもらえたら嬉しいです。